ゲーム音楽論では、今までゲーム音楽の作編曲と構造的特徴について考えてきましたが、自分はコード進行にも一定の傾向があると感じてます。
今回は、初期ゲーム音楽の王道的コード進行についてお話しますが、コード進行の話題は膨大な内容になってしまうため、個別曲については「ギター演奏・コード進行」の記事を見ていただくとして、今回は本当に代表的・特徴的なものに絞って解説しようかと。
少々専門的内容も出てきますが、イメージしやすいように有名曲の例を挙げながらやっていきます。
ゲーム音楽のコード進行の特徴
ゲーム音楽は比較的短い区間をループする構造のものがほとんどで、初期のものは16小節とか32小節、発展期以降も1ループ1分から2分くらいが主流です。
一般の音楽だと循環コード(2小節から16小節くらいで延々と繰り返すコードパターン)を使って短いループを作るのが一般的ですが、ゲーム音楽の場合、短い中で転調しまくったり、Cメロ・Dメロまで入れてきたりと、極力多彩な展開を付ける傾向があるのではないでしょうか。
つまり、時間当たりの音楽の内容が濃いという事なのですが、コード進行も濃い内容がコンパクトにまとまっているものが多く、音楽の学習にも最適だと思います。
時代によるコード進行の変化
ゲーム音楽のコード進行の作り方は、年代によっても変化してきました。
専任作曲家の少なかった1984年頃までは1ループも短く、1コードから3コードくらいの単調なものがほとんどでしたが、1985年頃から徐々に起承転結のある凝ったものが増えていき、ファミコン全盛期の1987年から1988年頃には「コンパクトに起承転結を入れ込んでループさせる」という技術は完成の域に達します。
スーファミ時代に入るとゲーム音楽作曲家が増えた事と、ハードウェアの向上によるアレンジの自由度向上という事があったため、コード進行もバラエティー豊かになっていきました。
その結果、今回紹介するような王道コード進行のようなものの比率は相対的に下がっていくのですが、王道コード進行のような手法は「失敗の少ない定番の作り方」としてずっと受け継がれていき、「ゲーム音楽らしさ」の一つの大きな要素を形成しているのです。
王道的コード進行
では、初期ゲーム音楽の王道的コード進行の実例を挙げていきますが、文中で出てくる独自用語(例:エンタテイメント型メロディー)などは前回の記事で解説していますので、予備知識としてご一読をお勧めします。
メジャー3コード+α
メジャーキーの3コード(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)は一般的な基本コード進行であり、ゲーム音楽特有の進行というわけでありませんが、初期の「エンタテイメント型メロディー」は、ほとんどこれで出来ています。
3コードといっても、本当にⅠ・Ⅳ・Ⅴの3つのみで完結しているものだけでなく、Ⅱm(またはⅡ)・Ⅲm(またはⅢ)・Ⅵm(またはⅥ)・Ⅶm7(♭5)のコードを組み合わせて展開させたものを含みます。典型例は以下のようなものです。
- リブルラブル
- パックランド
- スーパーマリオ地上のテーマ
- ドラクエ「序曲」
- バブルボブル

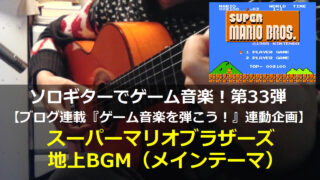

マイナー3コード+α
「マイナー3コード+α」は、上記の「メジャー3コード+α」のマイナー版で、マイナーキーの3コード(Ⅰm・Ⅳm・Ⅴ)を中心に作られる進行です。
次に挙げる「マイナー下降進行」と代理関係にあるので、同じカテゴリーにするか迷ったのですが、バリエーションも多いので分けて解説することにします。
「マイナー3コード+α」は、メロディーの出だし部分が、Ⅰm→Ⅳm(またはⅣ)、Ⅳm→Ⅰm、Ⅰm→Ⅴ(またはⅤm)、Ⅴ→Ⅰmで始まるパターンが多いです。
応用として、Ⅰm→Ⅱ7(Ⅴのセカンダリードミナント)というパターンも良く使われますが、その場合Ⅰm→Ⅱ7(onⅠ)という音使いが多用されます。
全体的にメジャー3コードより捻り(=臨時記号つきの音)が多いですよね。
また、メジャー3コード+αと同じく、Ⅱm7(♭5)・♭Ⅲ・♭Ⅵ・♭Ⅶを使用して展開を付けているものを含みますが、♭Ⅵ・♭Ⅶの使い方によっては、次に解説する「マイナー下降進行」にかなり接近します。典型例は以下のようなものがあります。
- 魔界村メインBGM
- ドラクエ3「冒険の旅」
- ストリートファイター2「リュウのテーマ」
- アクトレイザー「フィルモア」(Ⅰm→Ⅳのパターン)
- 悪魔城伝説「ビギニング」(Ⅰm→Ⅱ7のパターン)


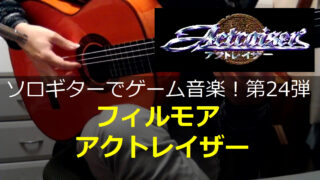
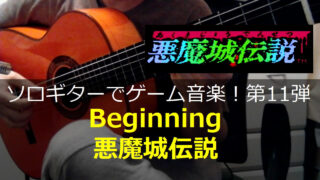
マイナー下降進行
「マイナー下降進行」は、マイナーキーのⅠmやⅣmからの下降進行を基調にするもので、例えばAマイナーキーなら、Am→G、Am→F、Dm→Cというような進行を起点とするものです。
フラメンコでもよくある進行なのですが、ゲーム音楽の場合、JMM型の進行といえます。この進行の典型例は以下のようなものになります。
- 悪魔城ドラキュラ「Vampire killer」「Bloody Tears」
- シルフィードのタイトル曲
- ダライアス「Captain Neo」「BOSS7」
- Live A Liveメインテーマ
- 幻想水滸伝2「Reminiscence」




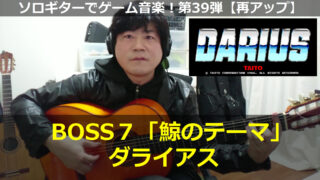
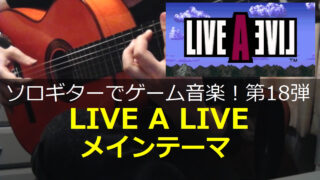

同主調混在メジャーキー
「同主調混在メジャーキー」は、メジャーキーを基調としながらも同主調マイナーキー(元のキーがCメジャーキーならCマイナーキー)のコードが出てくるもので、ゲーム音楽だと、いわゆる「コナミ進行」などが代表格でしょうか。
I→♭Ⅶ、I→♭Ⅵ、I→♭Ⅲなどから始まるものが多く、メジャーキーなんだけど切ない感じもする進行で、JMMとの相性も良いです。
このうち、I→♭Ⅶは非常に良く使われるパターンなのですが、複数の解釈が成り立つ場合が多く、注意が必要です。
例えば、CメジャーキーでC→B♭M7→Am7→A♭M7という進行の場合、C→C7(onB♭)→F(onA)→Fm(onA♭)という解釈も成り立つ場合が多いのですが、後者の場合「メジャー3コード+α」の進行と考える事も可能で、どちらの進行を採用するかは、メロディーや前後の流れから判断することになります。
この系統のコード進行がゲーム音楽に浸透したのは1985年頃からですが、非常に多用されたため、最もゲーム音楽らしい進行の一つとなっていています。典型例には下記のようなものがあります。
- スターソルジャー メインBGM
- スペースハリアー メインBGM
- ツインビー メインBGM
- グラディウス1面、4面、7面BGM
- ゼルダの伝説タイトル曲
- ドラゴンスピリット1面
- バハムートラグーンのタイトル曲と「ファーレンハイトのテーマ」
- 真・女神転生「エンディング」


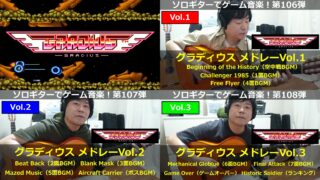
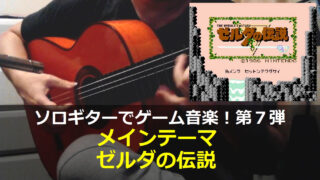


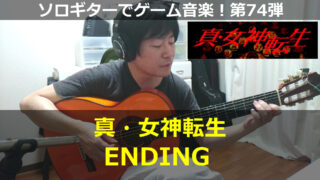
――上に挙げた4種類の進行はキャッチーなメロディーを作りやすく、応用・汎用性も高い進行で、ユーザーやメーカーにも受け入れられやすかったのではないでしょうか。
有名曲の実例を挙げましたが、1980年代後半から1990年代前半あたりはこれら4種類の進行を使った名曲が非常に多いですし、これらの基本進行を複数組み合わせたり転調を活用する事で、さらに複雑な音楽性を出す事も可能なのです。
ゲーム音楽で特徴的なコードテクニック
ここまで解説してきたのは、先駆者たちが作り上げた「こういうシーンならこういう進行でいけば間違いない」という王道的なコード進行パターンでした。
ここからは、もう少し細かい内容で、コード進行をゲーム曲に最適化させるテクニックをご紹介します。
方向性として、①少ない和音数で大きな効果が得られる②コンパクトにまとまっている③ループさせやすい、というような傾向で考えられた結果、こうしたコードテクニックが多用されるようになったものと思われます。
sus4ケーデンスの多用
ゲーム音楽では、sus4コード(メジャートライアドコードのド・ミ・ソがド・ファ・ソに変化したもの)を使った解決パターンを多用します。
主にⅤ7sus4→Ⅴ7などで、メロディーの終盤にオチを付けるために使われる他、Ⅰsus4→Ⅰ・Ⅰmで同主調転調の経過コードとして使われたりするパターンが多いです。
マイナーキーで最後だけメジャーキーに転調
マイナーキーでずっと進行して来て、最後だけ同主調メジャーキーのⅠに行くパターンも多用されます。
曲中ずっと「切ない、重い」感じできて、最後の最後で少し希望を持たせる明るい抜け感、みたいな感じで、RPGとかの展開をそのまま音にしたような、ゲーム曲として好まれる進行ですね。
先ほどのsus4ケーデンスと、このマイナー→メジャー切り替えの2つは、ベース音がルート(根音、CメジャーコードならC=ド)で鳴っていれば、3度の音の変化(ファ、ミ、ミ♭)のみで成立するので、少ない音数での微妙な調性表現がしやすいのだと思われます。
同主調コードの活用
上と同じようなメジャー・マイナーの切り替え手法の一つですが、同主調のダイアトニックコードを活用して調性を複雑化させる手法です。
これはゲーム音楽以外でも良く使われる手法なのですが、上で紹介した王道進行「同主調混在メジャーキー」は、この手法で成り立っているようなものだし、ゲーム音楽での使用頻度は非常に高いです。
オンコードの活用
オンコードというのは、ルート音以外の音をベース音に指定してあるコードで、分数コードとして表記されたり、コードネームの後に(onA)などが付いたりします。
オンコード・分数コードの解説
ゲーム音楽で特徴的なオンコードは、ドミナント7thコードの3度・7度の音をベース音にしたボイシングでしょうか。
3度ベースの場合は、ドミナントモーション時にベース音の跳躍を減らしてを滑らかにする効果があります。
7度ベースのコードも結構特徴的だと思います。例えば、「マイナー3コード+α」で紹介したⅠm→Ⅱ7(onⅠ)や「同主調混在メジャーキー」で解説したⅠ→Ⅰ7(on♭Ⅶ)というような進行が代表的です。
また、ベースラインを半音下降(または半音上昇)させたい時なども、オンコードを上手く使って調整してやると、まとまりのある進行が出来ます。
パッシングディミニッシュ
ゲーム音楽ではパッシングディミニッシュも多用されます。
パッシングディミニッシュの解説
ゲーム音楽の場合、以前解説したようにベースラインに制約が多かったため、ベースラインの跳躍を避けて半音進行に置き換えた結果、パッシングディミニッシュや上記の3度ベースのドミナント7thが多用されるようになったものと思われます。
また、そうやってディミニッシュコードに変換しておくと、そこを起点にして短3度平行移動が可能になるので、また違った展開が生まれたりして作曲上凄く使い勝手が良いんですよね。
――今回はコード進行の話をしましたが、こういう話はこれ以上掘り下げるとどんどん専門的になってくるので、基本をおさえたところで次に行こうと思います。
音楽理論に興味がある方は、自分が本名でやっている「後藤晃のフラメンコギターブログ」の「音楽理論ライブラリー」というコーナーにまとめてありますので、ご覧いただけたらと思います。
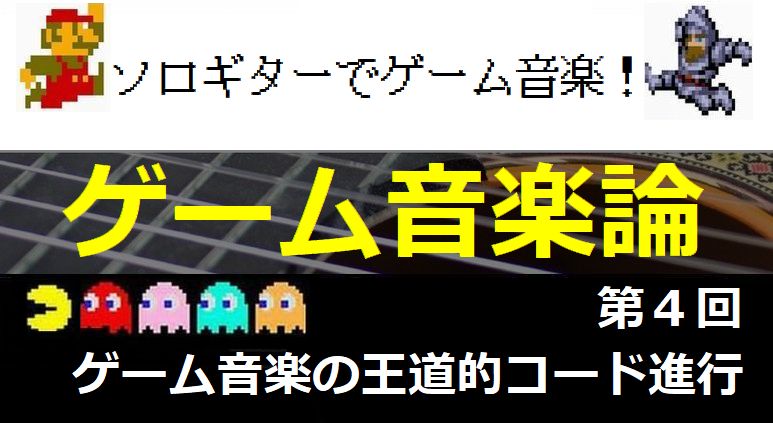
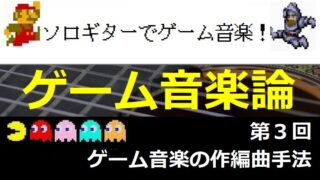




コメント