発売年月:1985年3月
機種:アーケードゲーム(Arcade Game)
メーカー:コナミ(KONAMI)
タイトル名:ツインビー(TwinBee)
曲名:ツインビーメドレー(TwinBee Medley)
作曲:コナミ矩形波倶楽部(福武茂/佐々木嘉則)
演奏難易度:☆☆★★★(普通)
ゲーム音楽ソロギター演奏動画・コード進行解説の第75弾は、ゲーム音楽の本格的発展の起点になった1985年3月のコナミ作品『ツインビー』の音楽をメドレーで演奏します。
ツインビーの作品概要
ツインビーはコナミが開発して1985年3月より稼働したアーケードゲームです。
翌年にファミコンに移植されて大ヒットしたので、ファミコンのゲームと認識している人も多そうです。
縦スクロールのシューティングゲームは1983年のゼビウス(ナムコ)で確立されたジャンルですが、ツインビーはこのジャンルに一石を投ずる革新性がありました。
まず、パステル調のポップな絵柄が目を引きます。敵キャラも野菜とかでしたよね(笑)
そして最大の特徴は2人同時プレイ+合体要素+多彩なパワーアップ要素という組み合わせでした。
2人同時プレイの縦スクロールシューティングは、ツインビーと同時期のものにエグゼドエグゼス(カプコン)などがありましたが、ツインビーのゲームシステムの完成度は群を抜いていました。
そして、その2人同時プレイが熱いゲームシステムと、親しみやすい絵柄がファミコンユーザーのニーズに合致して、ファミコン版の大ヒット(100万本)に繋がったんだと思います。
バブルシステムと当時のゲーム音楽事情
ツインビーは、コナミが満を持して出した業務用新筐体「バブルシステム」の第1弾タイトルでした。
少し後に出たグラディウスもバブルシステム用のタイトルです。
バブルシステムには波形メモリ音源が搭載されていました。
ですが、この後すぐにアーケードゲーム業界はFM音源への本格的移行時期に入って、結果としてバブルシステムに注力したコナミは微妙な立ち位置となってしまいます。
結局、翌年の1986年にはコナミもFM音源へと移行していますが。
なお、バブルシステムで培った波形メモリ音源のノウハウはMSX向けのSCC音源にしっかり活かされています。
そんなタイミングで発表されたツインビー(1985年3月)とグラディウス(同5月)ですが、ゲーム音楽的には当時の業界やゲーマーにかなりのインパクトを与えたものでした。
まず、1985年春の段階では、まだFM音源を採用した国産アーケードゲームは存在しませんでした。
1985年1月にNECからFM音源搭載のPC-8801mkⅡSRが発売されてゲーム業界のFM音源時代が始まりましたが、アーゲードゲームではアメリカ製のマーブルマッドネス(アタリ、1984年12月)が春頃から日本のゲームセンターでも稼働したりしていましたが、国産アーケードゲームでは1985年5月の戦場の狼(カプコン)が最初で、本格的に普及したのは1985年秋以降でした。
なので、ツインビーやグラディウスが出た段階では、ナムコを除いた他社はPSG音源だったため、波形メモリ音源でも十分に新鮮な魅力を感じられました。
自分は最近までグラディウスはFM音源だと思っていたくらいです。
このあたりの事は「ゲーム音楽史」に詳しく書いています。
ツインビーの音楽
ポップな絵柄とともに、キャッチーな音楽もツインビーの大きな魅力でした。
覚えやすいメロディーなので、記憶している人は多いと思います。
作曲は福武茂さん、佐々木嘉則さんのお2人が担当していますが、どちらがどの曲を作ったのかは不明です。
コナミ矩形波倶楽部発足後は、二人とも矩形波倶楽部の所属となり、クレジットもコナミ矩形波倶楽部の名義が使われています。
では、簡単にですが、お二方の紹介をさせていただきます。
福武茂さん
本名:福武茂(ふくたけ しげる)
通称:FANCY FUKUTAKE
福武茂さんに関しては、ほとんど情報を得られませんでしたが、ツインビーの他にハイパーオリンピックや恋のホットロックを手掛けていたようで、そうしたクレジットを見る限り、かなり初期の頃からコナミに在籍していたと思われます。
佐々木嘉則さん
本名:佐々木嘉則(ささき よしのり)
通称:モアイ佐々木
1984年頃からコナミに在籍。初期はロードファイター、新入社員とおる君などを手掛け、ツインビーの少し後には、夢大陸アドベンチャー、魔城伝説1&2、火の鳥などのMSX作品を担当しています。
グラディウス3面のモアイ像のモデルになった人物として一部では有名で、「モアイ佐々木」の通称はそれに由来しています。
1990年頃、サウンドクリエイターからプログラマーへ転向しています。
メドレーの演奏内容
今回はギターアレンジしやすそうな曲をメドレーにしましたが、正式な曲名を演奏順に列挙します。4曲+ジングル3つですね。
- 「Credit」(コイン投入)
- 「Start」(ゲームスタートのジングル)
- 「Twinbee’s Home Town Song」(メインBGM)
- 「Power Up」(パワーアップのジングル)
- 「Fantastic Power」(パワーアップBGM)
- 「Normal Ranking」(ノーマル・ネームエントリー)
- 「Top Ranking」(ハイスコア・ネームエントリー)
リズムトラック作成が一苦労【ソロギター演奏】
今回はオリジナルのアーケードゲーム版から採譜してアレンジしました。
キーはセクションごとに変わりますが、それもアーケード版と同じにしています。
- メインBGM=Cメジャーキー
- パワーアップ=Dメジャーキー(【コード進行のポイント】を参照)
- ノーマルエントリー=Fメジャーキー
- ハイスコアエントリー=Aメジャーキー
まず、演奏用のリズムトラックを作るのがかなり時間がかかりました。
このメドレーはテンポチェンジが激しいので、リズムトラックは使わないで完全ソロギターで良いんでは?とも思いましたが、練習するときにリズムトラック入れた方がいい感じだったので、頑張ってテンポチェンジをプログラムしました。
演奏面ではフラメンコ要素も入れましたが、メドレーにしたためサイズが長くなって暗譜も大変なので、アレンジはシンプルにしました。
それでも通して弾くのは結構大変で、星3つくらいの難易度はあると思います。
ツインビー「Twinbeeメドレー」コード進行
Credit&Start
|C|
|C|C|C F|G|
Twinbee’s Home Town Song
|C|C|B♭|B♭|
|C|C|B♭|B♭|
|C|C|B♭|B♭|
|C|C|B♭|B♭|
|Am|Am|G7|G7|
|Am|Am|G7|G7|
|C|C|F|F|
|Csus4|Csus4|F|G7|
|Csus4|Csus4|F|G7|
|F(♯11)|F(♯11)|CM7|CM7|
|F(♯11)|F(♯11)|CM7|G7|
|Am|Am|G7|G7|
|Am|Am|G7|G7|
|F|G7|A♭|B♭|
|C|
Power Up
|F|F|B♭|B♭|
Fantastic Power
|D|D7|C6|D7|
|D|D7|C6|D7|
|CM7|D7|CM7|D7|
|D|D7|C6|D7|
|D|D7|C6|D7|
|CM7|D7|CM7|D7
Normal Ranking
|B♭ B♭M7|B♭7 Gm7|Am7|Dm7 C7|
|B♭ Bdim7|Gm C7|F7|F7|
|F7|
Top Ranking
|E7|E7|
|A|A|G|A|
|A|A|G|A|
|D F|A|
コード進行分析
Credit&Start
■Cメジャー
|Ⅰ|
|Ⅰ|Ⅰ|Ⅰ Ⅳ|Ⅴ|
Twinbee’s Home Town Song
|Ⅰ|Ⅰ|♭Ⅶ|♭Ⅶ|
|Ⅰ|Ⅰ|♭Ⅶ|♭Ⅶ|
|Ⅰ|Ⅰ|♭Ⅶ|♭Ⅶ|
|Ⅰ|Ⅰ|♭Ⅶ|♭Ⅶ|
|Ⅵm|Ⅵm|Ⅴ7|Ⅴ7|
|Ⅵm|Ⅵm|Ⅴ7|Ⅴ7|
|Ⅰ|Ⅰ|Ⅳ|Ⅳ|
|Ⅰ|Ⅰ|Ⅳ|Ⅴ7|
|Ⅰ|Ⅰ|Ⅳ|Ⅴ7|
|Ⅳ|Ⅳ|ⅠM7|ⅠM7|
|Ⅳ|Ⅳ|ⅠM7|Ⅴ7|
|Ⅵm|Ⅵm|Ⅴ7|Ⅴ7|
|Ⅵm|Ⅵm|Ⅴ7|Ⅴ7|
|Ⅳ|Ⅴ7|♭Ⅵ|♭Ⅶ|
|Ⅰ|
Power Up
■Fメジャー
|Ⅰ|Ⅳ|
Fantastic Power
■Dメジャー
|Ⅰ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
|Ⅰ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
|♭Ⅶ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
|Ⅰ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
|Ⅰ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
|♭Ⅶ|Ⅰ7|♭Ⅶ|Ⅰ7|
Normal Ranking
■Fメジャー
|Ⅳ ⅣM7|Ⅳ7 Ⅱm|Ⅲm7|Ⅵm7 Ⅴ7|
|Ⅳ ♯Ⅳdim7※1|Ⅱm7 Ⅴ7|Ⅰ7|Ⅰ7|
|Ⅰ7|
Top Ranking
■Aメジャー
|Ⅴ7|Ⅴ7|
|Ⅰ|Ⅰ|♭ⅦM7|Ⅰ|
|Ⅰ|Ⅰ|♭ⅦM7|Ⅰ|
|ⅣM7 ♭ⅥM7|Ⅰ|
※1 Ⅴ7の代理
コナミ進行の見本市【コード進行のポイント】
メインBGMの「Twinbee’s Home Town Song」ですが、これは元祖コナミ進行ですね。
Cメジャーキーですが、同主調のCマイナーキーから拝借してきたB♭(♭Ⅶ)やA♭(♭Ⅵ)を多用します。
コナミ進行の典型はV→♭Ⅵ→♭Ⅶ→Ⅰというものですが、最後がもろにこれですよね。
パワーアップBGMの「Fantastic Power」はCM7とD7の2つしかコード出てこないんですが、逆に解釈が難しく、ぱっと思いつくだけで以下の4通りの解釈ができます。
- CメジャーキーのⅠM7とⅡ7
- GメジャーキーのⅣM7とV7
- Eメジャーキーの♭ⅥM7と♭Ⅶ7(コナミ進行解釈)
- Dメジャーキーの♭ⅦM7とⅠ7
自分はこの中で一番ひねくれていそうな4.のDメジャーで解釈したんですが、以下の理由です。
- ギターで終止を付けてみるとDメジャーが一番しっくりくる
- この作品は他の曲もⅠ→♭Ⅶという動きが骨組みになっている
「Normal Ranking」も、キーについては幾つかの解釈が可能ですが、動きからするとFメジャーぽいかな。ジャズスタンダード曲にありそうな進行ですよね。最後がⅠ7になってるのがポイントです。
「Top Ranking」は今回の演奏中、一番シンプルで素直な進行ですが、最後がⅣM7→♭ⅥM7→Ⅰになっています。
メジャー7thコードを短3度移動してるんですが、コナミ進行のバリエーション的な使い方です。


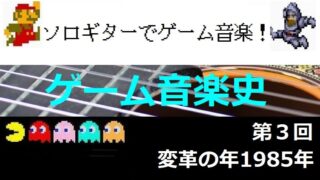
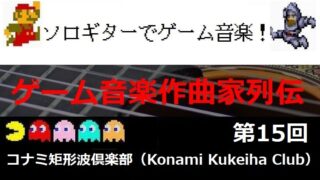
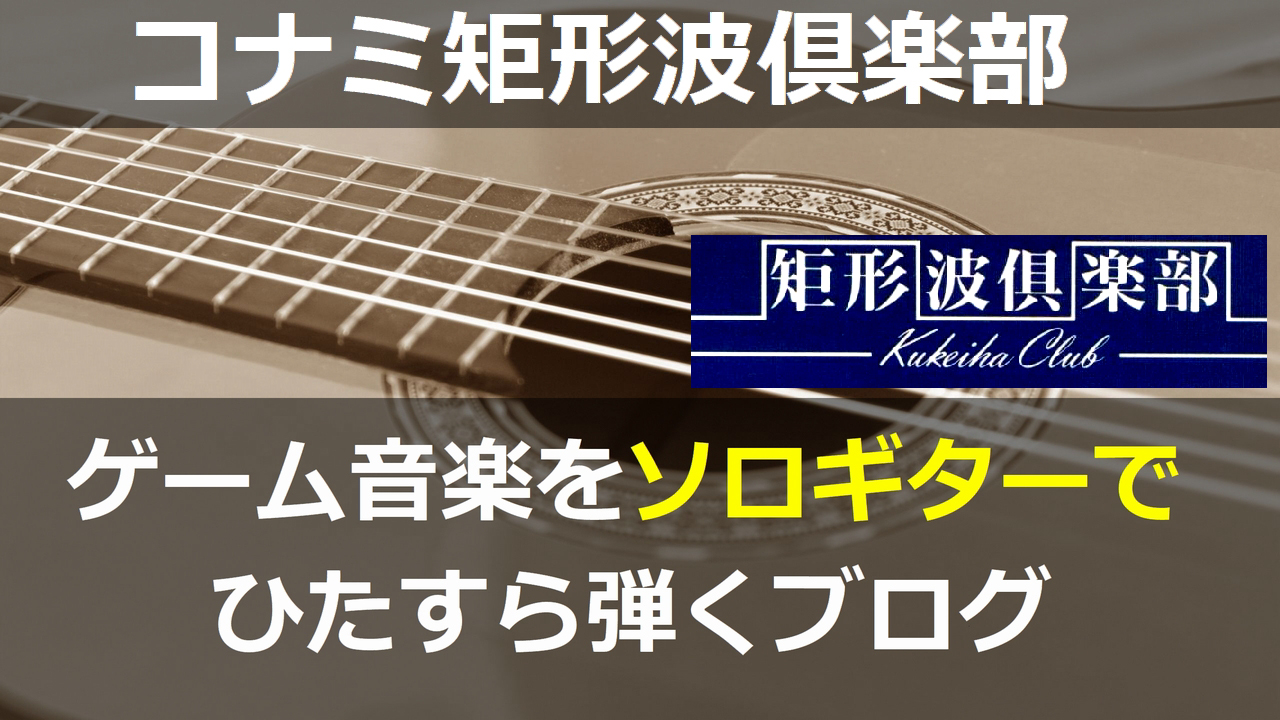
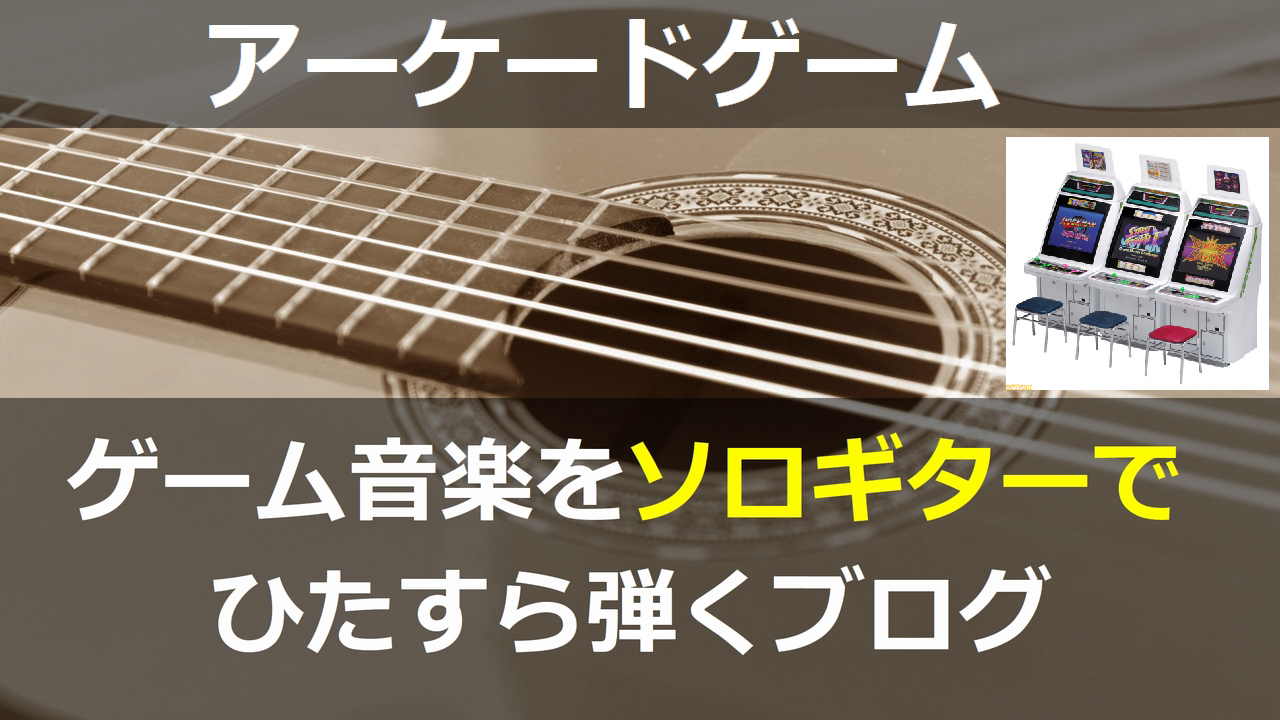
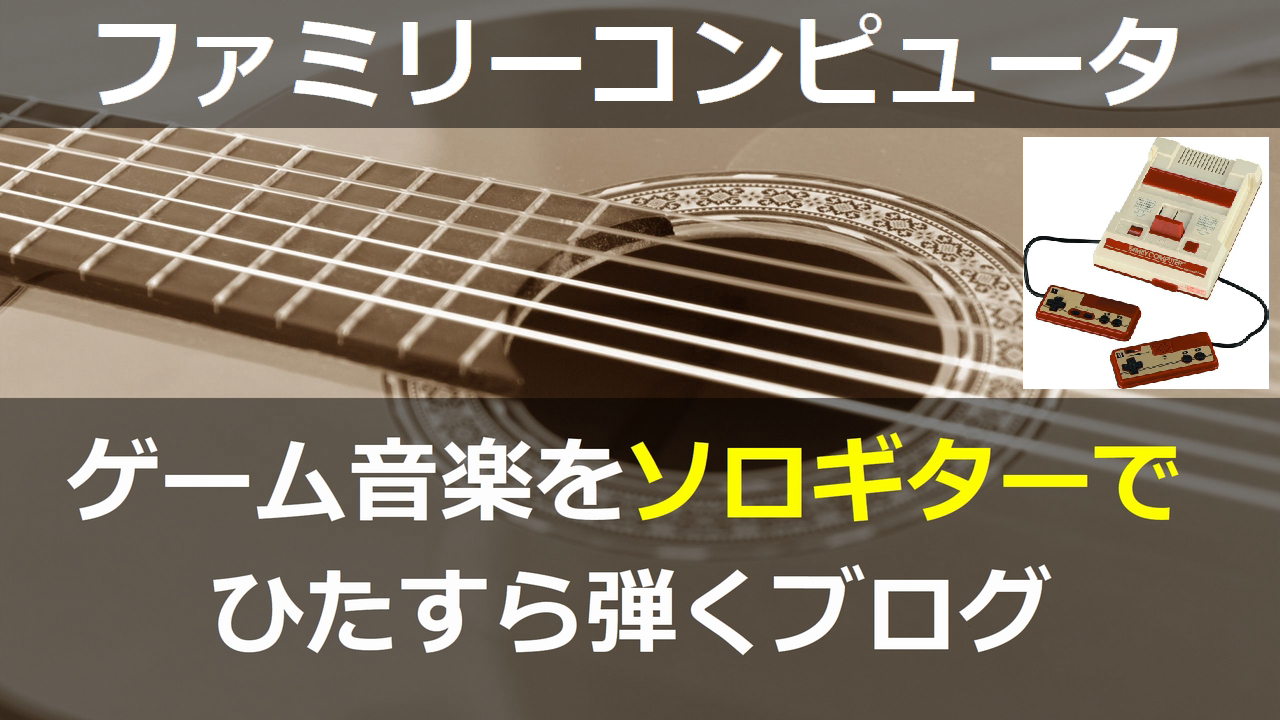
コメント