ゲーム音楽史では、前回までに第一次黄金期(1986年から1989年頃)の話をしましたが、アーケードゲーム主導で始まったゲーム音楽の発展も、最終的にはファミコンの爆発的ヒットでコンシューマー機に集約されていきます。
それを決定づけたのがスーパーファミコンでした。今回はスーパーファミコンが登場した時代のお話をします。
スーファミの発売
スーパーファミコンはファミコンの後継として、任天堂が1990年11月に発売した16ビットのCPUを持つ家庭用ゲーム機です。
グラフィック解像度はテレビに接続するという仕様上、PCには及びませんが、色数・スプライト数などファミコンと比較にならない進化をします。
そしてサウンドはPCM音源8chと、当時の家庭用ゲーム機としては強力なものでした。
セガのメガドライブも性能は良かったのですが、ファミコンのタイトルが1992年頃まで良いものが出続けたこともあって、ファミコンユーザーは後発のスーパーファミコンへ移行、任天堂はシェアの維持に成功します。
スーパーファミコンの普及によりアーケードゲームやPCとの性能差は小さくなり、わざわざゲーセンに通ったり、高いPCを買わなくてもハイクオリティなゲームが家庭で出来るようになったのです。
スーファミのPCM音源
スーパーファミコンのPCM音源は、基本的には現在のMIDI音源と同じものなんですが、PCM音源の本当に出始めの頃のものなので、現在のものとは比べ物にならないくらいスペックが低くて、リアルさやダイナミックレンジという面では全く話にならないものです。
しかし、それが逆に個性になっていて「スーファミの音」になっています。
これを今の基準で「低音質」と言ってしまえばそれまでですが、ゲーム音楽とは絶妙にマッチしていて「この音質が好き」というファンもたくさんいます。
なんというか、コンプレッサーを強くかけたような音圧感は中毒性がありますよね。プレステ以降のものはリアルになりすぎて、音質の印象はそれほど強くないですから。
そういう音質的なこともあって、スーファミの作品群はかなりのインパクトで記憶に刻まれています。
スーファミ時代前期のコンシューマーゲームお薦めタイトル
スーパーファミコンはファミコンのシェアを引き継いで、初期から優秀なタイトルが多数発売されていますが、ゲーム音楽という面で印象に残っているスーファミ初期のタイトルを紹介します。
F-ZERO(スーパーファミコン、任天堂)
スーファミ本体と同時発売。BGMは全て良曲。自分は「Big Blue」が好きです。
アクトレイザー(スーパーファミコン、エニックス)
古代祐三さん作品。これを聴いた植松伸夫さんがファイナルファンタジー4の音楽を作り直した、という逸話は有名です。それほどスーファミ初期作品としては突出していました。
ファイナルファンタジー4(スーパーファミコン、スクウェア)
植松さん作品の中でも映画音楽色(スターウォーズっぽい?)が濃いですよね。Ⅳの音楽は統一感があると思います。
ロマンシングサガ(スーパーファミコン、スクウェア)
伊藤賢治さんの出世作。ロマサガは1作目からイトケンサウンドが確立されていますね。バトル曲が人気ですが、自分的には街とかエピソードで流れる音楽もヒーリングミュージックとしてツボです。
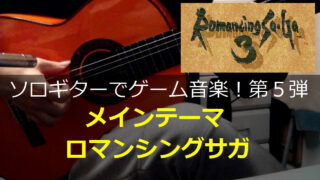
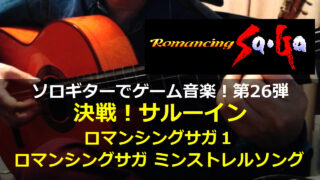

天外魔境2(PCエンジン、ハドソン)
久石譲さんが音楽を担当しています。「Lマップ通常」が秀逸。
スーパーマリオカート(スーパーファミコン、任天堂)
これの音楽はテンション上がりますよね。自分は「ノコノコビーチ」「レインボーロード」が好きです。
ドラゴンクエスト5(スーパーファミコン、エニックス)
この作品からドラクエの音楽もスーファミ音源になって、よりスケールアップして表現されています。Ⅴの音楽はすぎやまこういちさんのファンの間では賛否あるようですが、自分はかなり好きです。「王宮のトランペット」「街は生きている」「愛の旋律」そして「結婚ワルツ」など名曲が多いと思います。
真・女神転生(スーパーファミコン、アトラス)
音楽担当は増子司さん。女神転生の音楽はスーファミになってから一気に進化しました。音楽もPCM音源になって、とくにベースラインがちゃんとベースの音で出るようになったのは大きいと思います。自分は「銀座」「自宅」「邪教の館」「四天王の館」「廃墟」「エンディング」などが好き。
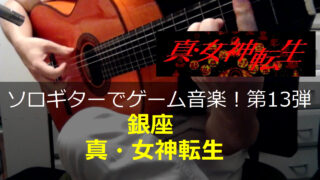
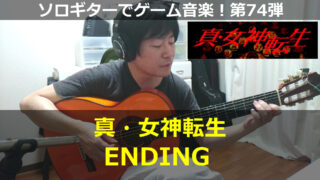
ウィザードリィ5(スーパーファミコン・PCエンジン、アスキー)
羽田健太郎さんが音楽を担当。オープニング曲が圧巻ですが、これはヘンリー・パーセル作曲の原曲があるようです。
ファイナルファンタジー5(スーパーファミコン、スクウェア)
Ⅳとまた雰囲気が違いますが、Ⅴは音楽の幅が広くてカラフルな印象です。「メインテーマ」「飛龍のテーマ」「古代図書館」「四銃士のテーマ」「ビッグブリッヂの死闘」「新しき世界」など個性的で印象深い曲が多かったです。

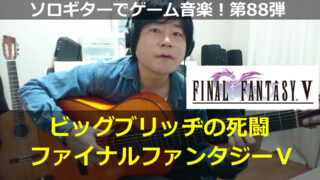
イーハトーヴォ物語(スーパーファミコン、ヘクト)
マイナータイトルですがタイトル曲は名曲であり、一聴の価値ありです。
スターフォックス(スーパーファミコン、任天堂)
音楽は平澤創さんが担当。自分は「コーネリアのテーマ」が凄く好きです。
聖剣伝説2(スーパーファミコン、スクウェア)
菊田裕樹さんのデビュー作品。これのタイトル曲「天使の怖れ」のフラミンゴが飛んでいくところは鳥肌でした。他にも「少年は荒野を目指す」「子午線の祀り」「危機」など名曲多数です。
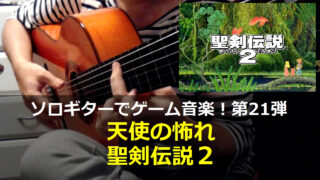
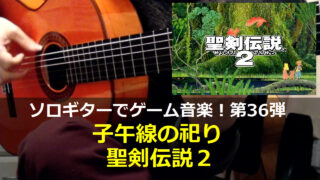
悪魔城ドラキュラX(PCエンジン、コナミ)
アレンジがバブル時代から90年代初頭の雰囲気で、他の悪魔城シリーズとカラーが違いますが「乾坤の血族」「SLASH」「op.13」など良曲多数です。
ロマンシングサガ2(スーパーファミコン スクウェア)
ロマサガ3部作では一番落ち着いた雰囲気の音楽ですが、自分は伊藤さんのバラード系、オーケストラ系大好きなので歓迎でした。
――これでもかなり厳選したんですが、スーファミは紹介したいタイトルが非常に多いです。最盛期の1994年から1995年は次回扱います。
対戦格闘ゲームブーム【ストリートファイター2】
スーパーファミコンの登場によって完全にシェアを奪われたかに見えたアーケードゲーム業界ですが、ところがどっこい、劇的に復活します。
ストリートファイターⅡ(1991年3月、カプコン)からの対戦格闘ゲームブームです。
自分は、スト2は主にスーファミでスト2ターボとスーパースト2をプレイしていました。少し後にプレステでストZEROもやりました。
これはかなりハマって、友達や妹と連日対戦していたので音楽はしっかりおぼえてます。
主にリュウ、ケンとかサガット(持ってたのがターボだったので)とかの飛び道具&コマンド系を使ってましたが、昇竜拳コマンド失敗であっさり負けるパターンが多かったです(笑)


このブームは、プレイヤーが自分の技術を高め、家庭内では不可能な不特定多数の対戦相手とプレイする、ということに着目したシステムが大成功し、再びゲーセンに人が集まるようになりました。
大会なども盛んに行われ、各社とも対戦格闘型のゲームを出してきています。
代表的なものに以下のようなものがあります。
- SNKの餓狼伝説(1991年)
- セガのバーチャファイター(1993年)
- ナムコの鉄拳(1994年)
このブームは長く続き、90年代後半にピークを迎えますが、2000年以降もギルティギアシリーズやBLAZBLUEシリーズなど一定数のヒット作が出続けています。
この時代のタイトーのシューティング作品
この時代のアーケードゲームの音楽に関しては格闘ゲーム以外にも良いものがあります。
完全に自分の趣味かもしれませんが、この時期のタイトーのシューティングゲームの音楽は非常に素晴らしいです。すべてZUNTATAのメンバーが音楽を作っています。
メタルブラック
渡部恭久さん初期の代表作
グリッドシーカー
古川典裕さん作品
ダライアス外伝
小倉久佳(OGR)さん作品
SNK ネオジオ(NEO・GEO)
対戦格闘ゲームブームのもう一方の立役者であるSNKですが、ストリートファイターⅡの登場と前後してネオジオ(NEO・GEO)というプラットフォームを出しています。
ネオジオはアーケードゲームと家庭用で同じ基盤を使用し「アーケードゲームと全く同じものが家庭でもプレイできる」というのが売りでした。
価格は本体58000円、ROMカートリッジが30000円以上と、かなり高額でしたが、家で練習してゲーセンで対戦する、というヘビーユーザーの需要でそこそこヒットしました。
PCのゲーム音楽の状況【1990年代前半】
同時代(1990年代前半)のPCは1991年ごろから普及し始めたDOS/Vパソコン(windowsPC)と、NECのPC-98シリーズがシェアを2分することになります。
ホビー用途ではX68000、FM-TOWNSも生き残っていますが次第にシェアを失います。
ゲームのほうは、アダルト系や高度なシミュレーションが中心となり、あまり一般向けではありませんでした。
このあたりのPCゲームはあまり詳しくありませんが、音楽の良いタイトルとしてX68000版悪魔城ドラキュラを挙げておきたいです。
サウンドはFM音源中心からPCM音源へ、さらにはデータを音源チップで再生する形でなく、現在のようなwav(CDなどのリニアPCMをデータファイル化したもの)などの波形を直接再生するオーディオファイル形式へと移り変わっていきます。
1990年代前半の携帯ゲーム機市場
1989年に発売されたゲームボーイは低年齢層中心にロングヒットを続け、90年代前半はゲームボーイタイトルも音楽はかなり充実しています。
1990年代前半のお薦めゲームボーイタイトル
この年代のゲームボーイのタイトルのうち、音楽が素晴らしいものをあげていきます。
Saga2秘宝伝説(スクウェア)
伊藤賢治さんの初期作品。名曲「伝説は始まる」の他、数々のバトル曲はすでにイトケン節が炸裂しています。
ネイビーブルー90(USE)
音楽が良いのは一部では有名な作品。
聖剣伝説(スクウェア)
これも伊藤賢治さんの初期作品。音楽的にはSaga2と同じ路線ですが、こちらも名曲多数です。
カエルのために鐘は鳴る(任天堂)
「とたけけ」こと戸高一生さんが音楽を担当。「王子の冒険」は名曲です。
他にウィザードリィ外伝シリーズ(アスキー)、ラストバイブルシリーズ(アトラス)なども良いですね!
ゲームギア
1990年10月にセガからゲームボーイに対抗した携帯ゲーム機、ゲームギアが発売されます。
ゲームギアはSTNカラー液晶を採用し、セガマークⅢと同等の性能がありました。
ただ、当時の技術ではカラー液晶はまだ時期尚早だったようで、価格が19800円と高額になったのと、電池持ちが致命的に悪く、ゲームボーイのシェアを奪うには至りませんでした。
サウンドはPSG3音+ノイズで、こちらはゲームボーイのほうが優れていました。
ゲームギアオリジナルのゲーム音楽としては、コンパイルのGGアレスタシリーズなどが有名です。
――次回はスーパーファミコンの全盛期でゲーム音楽第二次黄金期と言える、1995年前後のお話です。
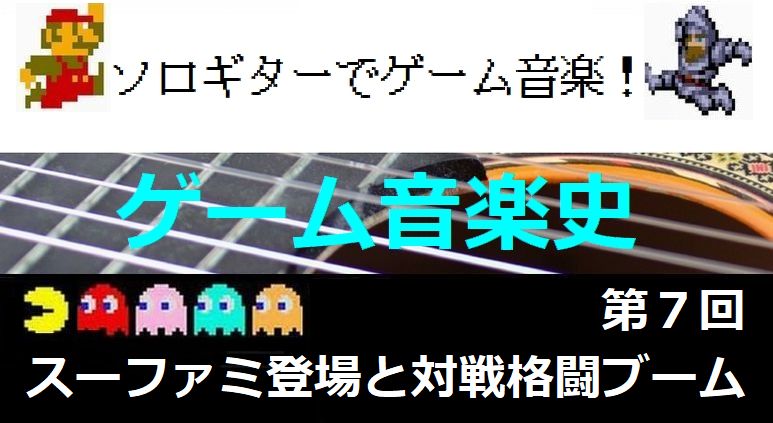
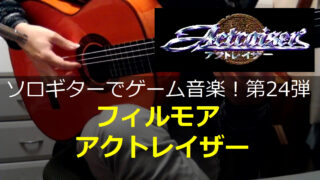
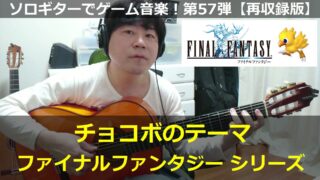



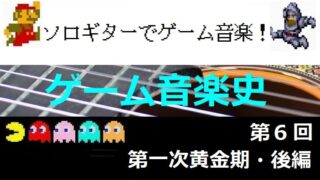
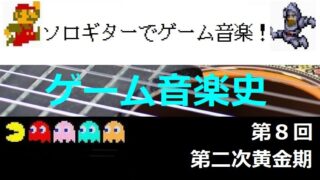
コメント