今回から新連載「ゲーム音楽論」をスタートいたします。
これまで当ブログで連載してきた「ゲーム音楽史」では、ゲーム音楽が誕生してから現在までの全体的な流れをみてきました。
今回からは「ゲーム音楽史」の内容を踏まえたうえで、もっと細かいゲーム音楽の話を「ゲーム音楽論」として展開していきます。
この「ゲーム音楽論」は音楽の中身の話がメインになるので、多少専門的な話も出てくると思いますが、なるべく分かりやすい言葉で書いていきたいです。
ゲーム音楽・ゲームミュージックというジャンル
「ゲーム音楽」という言葉は、クラシックやロックなどという音楽の特徴で分けた音楽ジャンルではなく、ゲームに使用されている音楽全般のことを指すので、言葉としては用途で分けられるジャンル、例えば映画音楽・環境音楽などに近いでしょうか。
その音楽的な内容は、時代や作曲者によって様相が異なりますが、多様な音楽ジャンルの複合体です。
こういう言い方だと、なんだか漠然としていて掴み所が無い感じになってしまいますが、自分は「ゲーム音楽らしい音楽」というのも確実に存在していて、音楽的な特徴もあると思っていますし、それを言語化・体系化してみようというのが、この連載の主旨でもあります。
日本のゲーム音楽のルーツ
ゲーム音楽に含まれる要素は非常に多様であり、作曲家個人個人それぞれのルーツミュージック・作曲の特徴ということにもなってきます。
例えば、ナムコの大野木宣幸さんならオールドファッションなアメリカの音楽、すぎやまこういちさんならクラシック音楽・歌謡曲という具合ですが、そうした作曲家の個人的な素養とは別に、ゲーム音楽全体に対して濃い影響を持つ音楽カテゴリーがいくつか存在していると思います。
テクノミュージックとYMO
ゲーム音楽と関連が深いジャンルとして、クラフトワークなどから始まったテクノミュージックがあります。
厳密にいうとテクノミュージックには以下の2種類があります。
- 1970年代頃から電子楽器の進化とともに誕生して1980年代にはテクノポップと言われていた音楽ジャンル
- 1980年代終わり頃アメリカのデトロイトで生まれた電子楽器と打ち込みのビートを駆使したクラブミュージックの一形態
これらは別物なのですが、テクノというジャンルの一般的な認識としては「テクノポップを含む、電子楽器を駆使した機械的シーケンスをベースに作られる音楽」ということで良いかと。
日本のテクノポップの草分けとして、YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)が有名ですよね。YMOのメンバーだった坂本龍一さんについて、こちらの記事で書きました。
YMOはゲーム音楽のCDをプロデュースしたり、演奏面でもチップチューン(ゲーム機等の音源を使った演奏を取り入れた音楽ジャンル)の走りのようなアプローチをやったりしていました。
ゲーム音楽の発生・発展年代も考えると、テクノミュージック、とくにYMOの音楽は初期のゲーム音楽の形成に絶大な影響を及ぼしたのではないでしょうか。
ゲーム音楽は、もともと電子音から始まったコンピューターで演奏される形態のジャンルだし、テクノミュージックとの親和性が高いのはある意味当然な事で、ファミコンのピコピコ音とテクノアレンジの相性もすごぶる良いものでした。
テクノからEDMへ
1990年代に入るとハウス・トランス・アシッドジャズ・デトロイトテクノなどのクラブミュージックが一般化し、他のジャンルと盛んにクロスオーバー。1990年代を通して、テクノを含むクラブ系の音楽ジャンルは渾然一体となりながら大発展して一大人気ジャンルとなりました。
現在、このカテゴリーの音楽はEDM(エレクトリック・ダンス・ミュージック)ということで統合されつつあります。
そして、1990年頃に始まったクラブミュージックブームの流れはゲーム音楽にもとり入れられていきました。
古代祐三さんも『ベアナックル』(1991年)でいち早くとり入れていたし、その後は、タイトーやケイブのシューティングゲームなどがテクノ・EDM系ゲーム音楽の流れを引き継いでいます。
EDM系の外部音源を切り貼りして作る制作方法は、大半をコンピューター上で制作するゲーム音楽とも相性が良いのではないでしょうか。
クラシック音楽
ゲーム音楽というジャンルの形成過程において、クラシック音楽・映画音楽からの影響は非常に大きなものだと思います。
最初期のゲーム音楽は専任の作曲者が居なかったこともあり、既存曲の流用が主流でしたが、とくに著作権的に使いやすいクラシック音楽のフレーズが多用されました。
その流れで、オリジナル曲中心の時代になっても耳に馴染みのあるクラシック音楽のフレーズをアレンジして取り入れたりする手法は残りました。
また、1990年代以降は音大出身者など正統的なクラシック系音楽教育を受けたゲーム音楽作曲家が増えたのと、ハードウェアの音源の進化によってオーケストラアレンジが一般的になっていったことがあり、作曲面・アレンジ面でもクラシック音楽要素のウエイトは高いものとなっています。
映画音楽からの影響
クラシック系音楽の中でも、ジョン・ウィリアムズ(スターウォーズとかスーパーマンの作曲家)をはじめとした映画音楽からの影響も大きなものがあると思います。
例えば、ドルアーガの搭とか、ファイナルファンタジーシリーズの一部の曲とか、かなりそれっぽいですよね。
日本のクラシック・映画音楽系作曲家でゲーム音楽への影響力が大きいのは久石譲さんでしょうか。
古代祐三さんが子供の時にに久石さんに師事していた話は有名ですが、久石さんの影響は世の中にジブリ作品が浸透した1980年代後半以降本格化しています。
久石さんの音楽と日本のゲーム音楽には「日本人的な感覚で作られたインストゥルメンタル音楽(久石さんは歌モノの作曲もしますが)」という共通点があり、影響を受けたであろうゲーム曲は数え切れません。
ロック音楽
ゲーム音楽は音源の発達とともに比較的初期の段階からロック音楽的表現も取り入れられて来ました。
ファミコン時代はPSGチップにオマケで付いているノイズチャンネルでドラムスを表現したりしていましたよね。
プログレッシブロック
プログレッシブロック(プログレ)は、1960年代後半から1970年代にかけて盛り上がったロック音楽の一形態です。
元々はシンプルな音楽であったロックにクラシックやジャズの手法を取り入れて、インストゥルメンタルパートを重視した知的な音楽に作り替えた音楽ジャンルで、代表的なアーティストに、キングクリムゾン、ピンクフロイド、イエス、ELP、ジェネシス、エイジアなどがいます。
1980年代から1990年代にデビューして活躍したゲーム音楽作曲家は、世代的に熱狂的なプログレファンが多く(しかも多作の人が多い)、プログレ要素がある楽曲もかなりの数に上ります。
プログレ派の代表格としては、植松伸夫さん、桜庭統さん、菊田裕樹さんなどが居ますが、東野美紀さん、河本圭代さんなどからもプログレの影響を感じますよね。
ハードロック
ハードロック・ヘヴィメタルは1980年代に隆盛を極めた音楽ジャンルですが、これがゲーム音楽に導入されたのは、増子司さん(女神転生シリーズが有名)のデビュー作『スターフォース』(1984年)の「ターゲットのテーマ」あたりからでしょうか。
増子さんの他にハードロック的な作曲をする初期の作曲家として、塩生康範さんや笹井隆司さんが居ますし、古代祐三さんも初期作品ではハードロック要素が強めでしたよね。
プレステ世代以降では、ガストやファルコムのゲーム音楽にハードロック要素は欠かせませんし、ギルティギアシリーズやブレイブルーシリーズを手掛けるアークシステムの石渡太輔さんなどはメタルスタイルに特化しています。
日本の大衆音楽と「クサメロ」
これは音楽ジャンルというわけではありませんが、日本のゲーム音楽にとって一番重要な要素かもしれない日本独特の「クサメロ」の歴史に触れておきたいと思います。
「クサメロ」は、日本人の心象を表すちょっと切ないメロディーの事ですが、その変遷は以下のようなものだと思われます。
民謡など
↓
軍歌・戦前戦中の唱歌
↓
演歌・歌謡曲・和製フォーク
↓
ニューミュージック
↓
メロディー重視派のJポップ
このように、日本の庶民が親しみ愛してきた大衆音楽には「クサメロ」は必須なものなのですが、初期のゲーム音楽は、この「クサメロ」が劇的に生かされたジャンルでもあると思います。
ゲーム音楽が誕生する少し前に隆盛を極めた初期アニソンや戦隊モノ主題歌なども「クサメロ」特化ジャンルなのですが、日本のゲーム音楽にみられるクサメロも同じ流れから派生しているのではないしょうか?
初期アニソンなどに比べると、ゲーム音楽は少し時代が新しいのと、インストゥルメンタル音楽ということで、より現代的・マニアックな要素が多いのですが、メロディーの作り方などは、共通の日本大衆音楽の血統を感じます。
ゲーム音楽とクサメロの関係については、こちらの記事でJMM(ジャパニーズメランコリックメロディー)として詳述しています。
クサメロ=JMMは、とくに初期の和音数や音色が貧弱な時代に、プレイヤーのテンションを高揚させ、ゲームを盛り上げるのに絶大な効果を発揮し、ゲーム音楽の重要要素として定着しました。
そう考えると、ゲーム音楽は日本古来の大衆音楽とテクノロジーの融合ということで、1980年代からの日本の大衆文化を最も的確に表現しているのかもしれませんね。
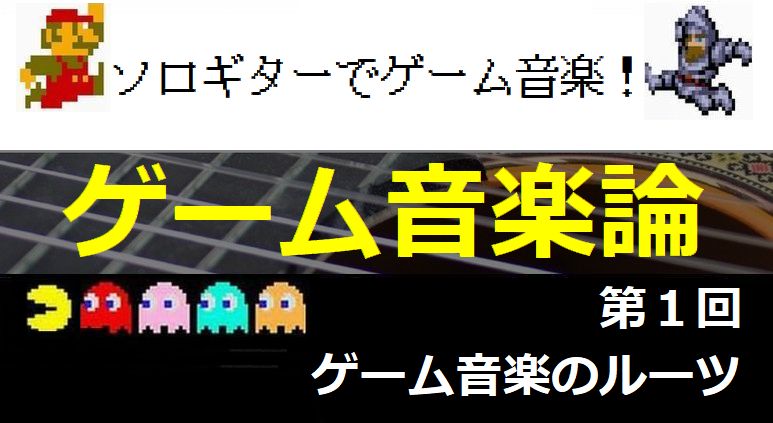

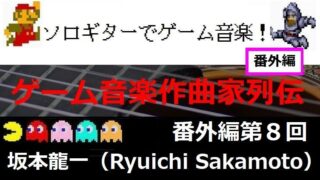
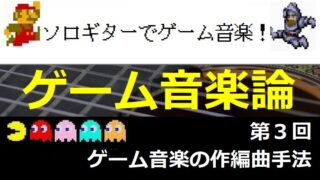
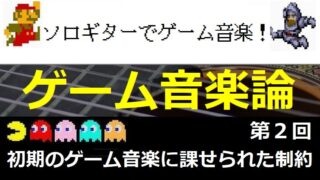
コメント