「ゲーム音楽論」では、今まで様々な角度から「ゲーム音楽らしさ」について解析をしてきました。
最終回となる今回は、今までやってきた内容をまとめつつ、ゲーム音楽の魅力の本質に迫ってみたいと思います。
※この記事は2019年1月に投稿したものですが、今回(2022年10月)大幅にリライトし、記事のテーマも変わったため、新URLで新規に公開することとしました。
ゲーム音楽の魅力の本質と影響力
これは自分個人の持論なのですが、ゲーム音楽の魅力は、この連載でやってきたように、様々なジャンルの音楽の要素を組み合わせて創造されるハイブリッドな魅力というのがその本質なのではないでしょうか。
さらに言うなら、初期の制作環境の制約は、ゲーム音楽を単なるフュージョン・クロスオーバー音楽の真似事に留まらせることなく、無二の個性を与える結果となっているのではないかと。
こういう事が可能となった背景には、まず、初期のゲーム音楽制作は他の音楽ジャンルでは許されないような実験的な事も好きに出来る自由な雰囲気があったと思います。
業界全体が立ち上がったばかりでフロンティア精神に満ちていた時代だったし、ファミコンの成功によって資金・人材が集まった事も大きかったでしょう。
また、制作面から見ても、初代プレイステーション時代以前は、ほぼ打ち込みで完結していたため、実験的に様々な要素を入れてみるという事も比較的容易だったと思われます。
――そうやって生み出された個性的なゲーム音楽は、本来インストゥルメンタル音楽に興味がないようなユーザーにも半ば強制的に届けられ、しかもループして繰り返し、繰り返し、聴かれることになります。
音楽をやっている人なら、このコンボの凄まじい破壊力が分かるのではないでしょうか。
自分の演奏や音楽を聴いてもらうということは、それが個性的なものであればあるほど大変なものですが、1980年代後半から1990年代のゲーム音楽には一般のインストゥルメンタル音楽では考えられないような環境と影響力があったのです。
異ジャンル要素のハイブリッド
「ゲーム音楽論」では、ルーツや初期の開発環境の考察に始まり、メロディー、アレンジ、コード進行、音階、リズムといった各要素の分析をしてきましたが、その中でメロディー・アレンジ・リズムの要素を以下のようなカテゴリーに分けて解説しました。
メロディータイプ
①JMM(ジャパニーズ・メランコリック・メロディー)型メロディー
②エンタテイメント型メロディー
③テクノ/ミニマル型メロディー
④クラシック型メロディー
アレンジタイプ
①ロック/フュージョン型アレンジ
②テクノ型アレンジ
③クラシック型アレンジ
リズムタイプ
①ロック型リズムタイプ
②テクノ型リズムタイプ
③ラテン型リズムタイプ
④クラシック型リズムタイプ
⑤ジャズ型リズムタイプ(使用頻度は少ない)
これら各カテゴリーの解説は以下記事で行っていますので、まだ読んでいない方はご一読を。
これら異ジャンルの要素同士のハイブリッド(複合・融合)によって、斬新な個性が生まれるのではないかと自分は考えています。
メロディータイプが4種類、アレンジタイプが3種類、リズムタイプが5種類あるので、単純計算で組み合わせは60通り。複数タイプの複合型を考慮するとさらに多くの組み合わせが考えられますが、この中で意外な組み合わせほど、斬新で個性的な音楽が生まれるという事は容易に想像出来るのではないでしょうか。
例えば、東方Projectならテクノロック系ビートのリズムセクションに濃いJMMメロディーが乗っている曲が多いし、悪魔城ドラキュラシリーズなら、1面BGMはクラシック型メロディー+ロック型アレンジの楽曲が多いですよね。
ロマンシングサガシリーズはバトル曲が有名ですが、あれはJMM型メロディー+クラシック型アレンジ+ロック/フュージョン型リズムという組み合わせで異彩を放っていました。
植松伸夫さんが担当していた時代のファイナルファンタジーは、JMM寄りのメロディーとクラシック型+ロック型の複合アレンジをベースに、植松さん独自のプログレ要素が付加される、といった感じでしょうか。
大抵、インパクトのある楽曲は、異なるカテゴリー同士のメロディーとアレンジとリズムが巧みに組み合わせられていますが、自分個人的にはJMM型メロディーの個性的な活用が日本のゲーム音楽最大の特徴、かつ最大の魅力となっているように思います。
ゲーム音楽の現在と未来
最後になりますが「現在のゲーム音楽」「未来のゲーム音楽」についても思うところを書いておこうと思います。
今まで「ゲーム音楽論」で解析してきたのは、「ゲーム音楽らしさ」が確立されるまでの、比較的初期のものが主な対象で、現在のゲーム音楽についてはあまり触れてきませんでした。
ゲーム音楽史でも書いていますが、プレステ1からプレステ2時代あたりでゲーム音楽の内容にかなりの変容があり、以後、BGM等は映画やアニメの劇伴に接近していきますが、メインテーマや主題歌などある程度独立した形の楽曲は一般の音楽と同様の制作方法がとられる事が多くなりました。
一方で、チップチューンブームからのフィードバックや、昨今のダウンロードプラットフォーム台頭によるレトロゲーム再評価の動きもあって、PSGやFM音源的な音色や作編曲手法がリバイバルして来たりと、一本道の進化ではない複雑な様相になっていますよね。
また、近年はインタラクティブミュージック(ゲームの場合、場面やプレイヤーの行動にあわせて自動的にアレンジが変化したりする)なども出現してきて大変興味深いですが、このあたりのジャンルはAI(人工知能)技術の進化の影響が大きいと考えられます。
AIの進化は凄まじいものを感じますし、音楽分野でも作編曲などはどんどん自動化されていくのかもしれません。
10年後のゲームにはインタラクティブミュージックを更に進化させたリアルタイム作曲アルゴリズムが採用されることになるかも知れませんね。ある意味、コンピューター技術の発展とともに歩んできた「ゲーム音楽らしい未来」ですが……。
――現在のゲーム音楽の「ゲーム音楽らしさ」を論じるというのは、音楽性も考慮すべき要素も広がりすぎていて、正直、自分の知見では難しいのですが、一つ言いたいのは、現在においても本連載で扱ってきたような要素は1980年代からの流れを継ぐゲーム音楽の本流であり、多くの人に「ゲーム音楽らしさ」を感じさせるものではないか?という事です。
ゲーム音楽論あとがき
「ゲーム音楽論」いかがでしたでしょうか?
当初は「ゲーム音楽史」の付帯資料的な形を予定していましたが、始めてみたら話題が広範囲に及び、途中、小難しい話になってきたり、自分自身どのへんまで主観で語っていいものか迷いながらの連載となりましたが、ゲーム音楽を理論的に掘り下げてみる、というのは一度やってみたかったんですよね。
音楽への感じ方は人それぞれのものがありますし「一人のゲーム音楽ファンの感じたこと」と捉えていただければ幸いです。ご愛読ありがとうございました!
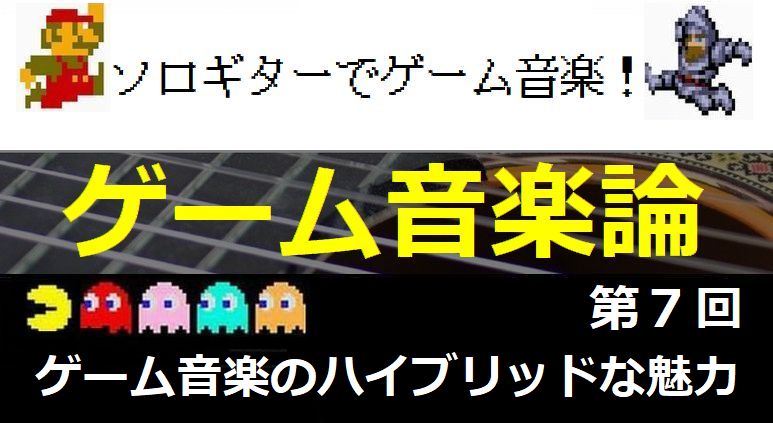
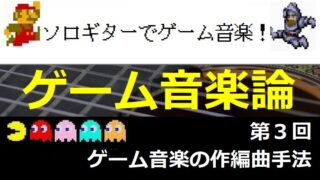
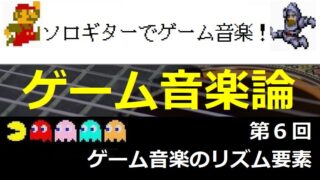
コメント