前回から新規スタートした「ゲーム音楽論」ですが、初回は「ゲーム音楽の形成に影響を与えた音楽」ということを考えてみました。
ゲーム音楽史の時代区分でいうと、初代プレステ時代あたりからゲーム音楽の構造が変わっていますが、この連載のメインテーマとなっている「ゲーム音楽らしさ」が形成されたのは主にそれ以前のスーパーファミコン時代までの事だと思います。
これは率直にいうと、同時発音数と限られた音色、メモリー容量などの厳しい制約に対応するための工夫から産まれているものです。
今回は、そうした初期のゲーム音楽の制作環境と、そこから生まれてきた音楽との因果関係について考察してみたいと思います。
同時発音数の制約
初期のゲーム音楽の音源の例をいくつか挙げてみます。
- 初期のナムコアーケードゲーム→1音高速切り替えによる疑似3和音
- 1984年頃までのアーケードゲーム、ファミコン、MSX、御三家PCなど→PSG3和音+ノイズ
- ナムコ「C15」→波形メモリ音源8和音
- PC-8801mk2SR→FM3和音+SSG3和音の6和音
- スーパーファミコン→PCM8和音
つまり、同時発音数が3音から8音くらいだったわけですが、これだと、ちょっと複雑な表現をするには全く足りませんでした。
一般的なMTRなどの音楽制作では、コード楽器があれば1チャンネルで和音表現が出来るので8チャンネルくらいあればなんとかなっていたのですが、この時代のゲームの音源の場合、トライアドコードを鳴らすだけで3チャンネルを消費してしまうので、コードや音の重なりがある表現は難しかったわけです。
こんな環境でしたので、コード感と奥行きを出すために独自の作曲・アレンジ手法が発達することになりました。
音色の制約
次は、もう1つの大きな要素「音色」について考えてみたいと思います。
ゲーム音楽に使用されてきた音源についてはゲーム音楽史でも簡単に触れていますがもう少し掘り下げてみましょう。
PSGと矩形波
ナムコの波形メモリー音源という「突然変異種」を別にすると、日本では1981年から1982年頃からPSG(プログラマブル・サウンド・ジェネレーター)が登場してきてゲーム音楽の発展が始まります。
それまでは独自の音源回路だったり、BEEP音(PCのマザーボードなどについている通知用の電子音)の発振周期をいじったりして、なんとか短い単音メロディーを出していた状態でした。
ゲームの世界に音楽をもたらしたPSGですが、これの音色は矩形波(BEEP音と同様のピーという電子音)を簡単なエンベロープ(立ち上がりや減衰など)加工をして作られていました。
それに加えてノイズ(全周波数が同時に出ているザーッという音。ゲームでは爆発音とか打楽器を表現するのに使われる)を出すことができました。
チップによっては、矩形波3音+ノイズで4音出せたものもあります。
ファミコンの内蔵音源
ファミコンの音源はPSGのカスタムチップを採用していて、矩形波2音+ノイズに加えて三角波(矩形波よりアタックや減衰が緩やかなポーという音)を出せたので、ベースパートを三角波に割り当てることが多かったようです。
さらにファミコン音源の矩形波は、デューティー比を変えることで、多少の音色変化が得られたため、一般のPSGより表現力が高かったのです。
PSGは「最低限の音楽表現が可能になった」という意味で革新的でしたが、上記のように音色バリエーションがほとんど無かった上に、高音域・低音域のピッチ精度の問題があって綺麗に鳴る音域が制限されていました。
波形メモリ音源
次に、1980年頃からナムコがアーケードゲームで採用し、コナミのSCC音源・ファミコンディスクシステム拡張音源・PCエンジンなどで使われた波形メモリ音源についてです。
こちらはPSGと異なり、音色波形をプリセットしておいて使うという方式で、音色の数や品質はチップのスペックに依存しています。
1980年代当時のものは低解像度の波形を極少数しかプリセット出来なかった上、強弱設定など細かい事はできませんでした。
なので、アタックの強弱感のある音色は全く適しておらず、PSG様の矩形波をベースとして、シンセ系・オルガン系のテイストが加味される「高級PSG」という趣でした。
FM音源
次は、1985年頃から普及したFM音源についてです。
これは簡単にいうとPSGをグレードアップして波形エディットを可能にしたもので、PSGでは不可能だった正弦波、ノコギリ波なども出すことができ、エンベロープも音色・トラックごとに詳細な設定が可能になりました。
ピッチの精度も向上し、中音域以外でも音痴になることがなくなり、ベースラインがボヤけたりという事も無くなりました。
ただ、音色はなんでも作れるかというと、やはりギターや打楽器、生ピアノなど強弱感のある音色や、ディストーションギターや人声のように波形が複雑に変化する音色は苦手でした。
逆に、シンセベースやシンセブラスなどの音色には独特の魅力があり、現在でもFM音源ならではの音色として現役で使われていたりします。
初期のPCM音源
最後に、FM-TOWNSやスーパーファミコンに採用されたPCM音源をみてみましょう。
これは、言わば波形メモリー音源のグレードアップ版で、生楽器などの音をサンプリングしたものをプログラム再生する方式ですが、その音質(=サンプリングレート)や強弱感(ベロシティ)などの精度はチップのスペックに依存します。
1985年頃からアーケードゲームでは「打楽器のみPCM音源」というパターンがありました。
打楽器は音程が無く(厳密にはあるんですが、ここではそこまでは突っ込みません)、サスティンや時間経過による波形変化も少ないため、サンプル数が少なくてもある程度リアルな表現が可能で、比較的初期のハードでも使用することができたわけです。
スーパーファミコンのPCM音源は、オーケストラやディストーションギターもある程度の再現が可能でしたが、サウンド用のメモリーが少なく解像度が低かったため、生演奏の音とはかけ離れていました。
ただ、その癖のある音色が逆に魅力的な個性になっていて、一聴してわかる「スーファミサウンド」となるわけですが。
これも、当時のサウンドクリエイターの努力で個性・魅力というところまで昇華出来たのだと思います。
音色の制約による影響
以上のように、スーファミ時代あたりまでは使用音色にもかなりの制約があり、これも作曲やアレンジに大きく影響していました。
作編曲手法の具体的な事は長くなりますので、今後少しずつお話ししていこうと思います。
ちなみに、この後の時代はCDDAによる生録音再生や高解像度のPCM音源でリアルな楽器音が出せるようになり、同時発音数の制約も無くなっていって、作編曲手法もどんどん一般の音楽に近付いていきます。
開発環境の制約
同時発音数や音色の制限という問題の他にも、初期のゲーム音楽開発環境には作曲やアレンジに大きく影響するような、開発環境の厳しい制約がありました。
メモリ容量との戦い
当時の開発環境で最も問題となっていたのはメモリ容量でした。
8ビットPCは普通はオンメモリで扱えるのが最大64キロバイト、ファミコンのロムカートリッジも同じくらいでした(ドラクエ1が64キロバイト)。
それでゲーム全ての処理を行うわけで、全体がカツカツのなか、音楽に割り当てられるメモリは極わずかでした。
ちょっとループが長くなったりアレンジが複雑になると、メモリに乗り切らなくなるという状態です。
移植版(機種は失念)のゼビウスのBGMは、たった2小節のループが入らず1小節ループにされていたり。
現在の環境からは信じがたい話ですが、当時はそんなギリギリの状態での開発だったのです。
それに、昔はメモリの単価が非常に高価だったので、初代プレステでも他のスペックに対してメモリはカツカツで、1990年代までのゲーム音楽の制作はメモリ容量からくる制約が大きかったようです。
人的・時間的な制約
初期のゲーム音楽制作環境は、人的・時間的なリソースの問題も大きかったと思われます。
初期のゲーム音楽は専任サウンドスタッフがやるようになったと言っても、基本1つのタイトルを1人で作曲・アレンジ・サウンドプログラム・音色作成・サウンドデバッグ、場合によってはサウンドドライバの開発や組み込み・効果音作成まで全部やるというスタイルが普通でした。
制作期間も数か月程度で、テストやデバッグの期間を差し引くと作曲・アレンジにあてられるのはごく短期間だったと思われます。
作曲家個人として曲はストックしていたと思いますが、一般の音楽制作より時間的に制約が大きいのは確かでしょう。
――結果的にこういう各種制約が作曲家の創意工夫を促し、ゲーム音楽の独自性ということにつながって行くのが音楽の面白いところですよね。
次回からは、今回みてきたような同時発音数・音色・開発環境の制約と作曲・アレンジ手法の関係についてお話していきたいと思います。
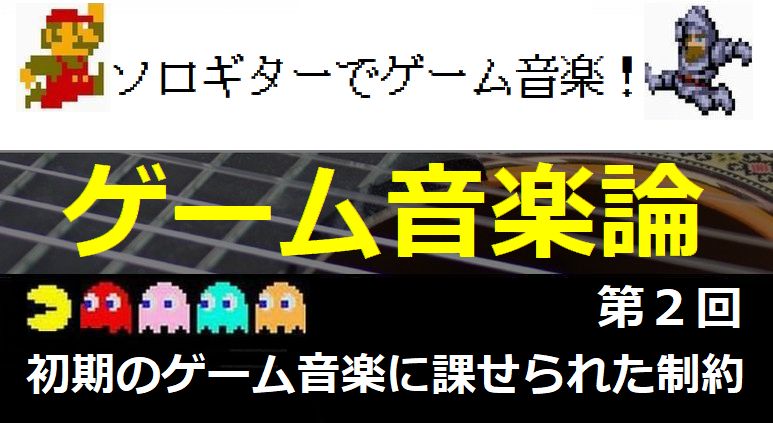
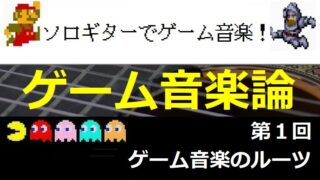
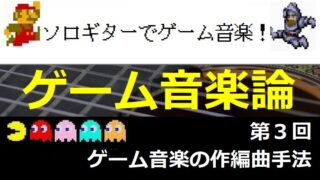
コメント
ファミコン時代のベースラインがシンプルだったのはこうでもしないと、メモリに入りきらないという苦肉の策でした。
この時代はアーケードですら、メモリが少なくて苦労することがあり、あの有名なアウトランも当初はLAST WAVEが入らず、他の曲を最適化してどうにか収めたとのことです。
PPPさん、コメントありがとうございます。お詳しいですね!
80年代当時はメモリ不足の問題もかなり大きかったでしょうね。
キロバイト単位でしたし。
アウトランは当時としては1ループ長かったしアレンジも音色も凝ってたから容量的にキツかったのは想像できます。
少し前のファンタジーゾーンは当時としてはベースラインが凝っていましたね
あのスラップの使い方は衝撃的でした。
あと、3和音環境での凝ったベースラインは
アレンジ詰めるのがすごく大変で下手にやると楽曲バランス崩壊するので
開発期間や人員の問題もあって(昔は一人で短期間で音色・効果音・サウンドデバッグまで全部やってたり)
ベースラインは無難にルートを鳴らしていた。
というのもありそうです。
そのへんもう少し考察して加筆するかもです。