
↑クリックで動画再生
発売年月:1987年8月
機種:ファミコンディスクシステム(Famicom Disk System)
メーカー:コナミ(KONAMI)
タイトル名:悪魔城ドラキュラⅡ 呪いの封印(Castlevania2 Simon’s Quest)
曲名:血の涙(Bloody Tears)
作曲:松原健一(Kenichi Matsubara、コナミ矩形波倶楽部)
演奏難易度:☆☆★★★(普通)
ゲーム音楽ソロギター演奏動画・コード進行解説の第89弾は『悪魔城ドラキュラ2 呪いの封印より』「Bloody Tears(血の涙)」を演奏いたします。これでドラキュラ三大名曲を制覇しました!
三大名曲制覇
悪魔城ドラキュラシリーズには「ドラキュラ三大名曲」と呼ばれるものが存在します。以下の3曲です。
- Vampire Killer(初出は1986年の初代悪魔城ドラキュラ)
- Bloody Tears(初出は1987年の悪魔城ドラキュラ2)
- Beginning(初出は1989年の悪魔城伝説)
このうち、「Beginning」は2018年6月17日に演奏動画をアップ、「Vampire Killer」は、昨年2020年6月6日に「悪魔城の日」として(6月6日→666の獣→悪魔→悪魔城みたいな連想で)アップしていて、いずれも6月に演奏しているんですよね。
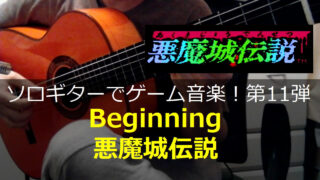

ドラキュラ三大名曲に関しては、上の2つの記事でも書いているので、そちらを読んでいただくとして、今回も6月6日悪魔城の日に三大名曲最後の1曲「Bloody Tears」をアップして、ついに三大名曲を制覇しました!Beginningから3年越しですねー。
今後、毎年6月6日は悪魔城関連楽曲をアップすることにしようかな……。
悪魔城ドラキュラ2 呪いの封印 作品概要
『悪魔城ドラキュラ2 呪いの封印』(以下、本作)は前作『悪魔城ドラキュラ』に続いて、ファミリーコンピュータディスクシステム用のソフトとして1987年8月27日に発売されました。
本作はステージクリア型の純アクションゲームだった前作に対し、RPG的な成長要素もある探索型のゲームシステムに変更されています。
また、昼と夜といった時間の概念も追加され、音楽も昼と夜で違う曲になっていました。
悪魔城ドラキュラ2の音楽
前作『悪魔城ドラキュラ』はROMカートリッジ用に開発されていたのを急遽ディクスシステム用に変更して発売した、という経緯があってディスクシステムの拡張音源は使われていませんでしたが、本作は最初からディスクシステム用に開発されていて、音楽には拡張音源が使用されています。
ちなみに、後に発売された北米版はROMカートリッジだったため、音源の差を補うために楽曲のアレンジ変更が施されました。
この後の『悪魔城伝説』の頃になると、ディスクシステムのプラットフォームは下火になってきたため、再びROMカートリッジに回帰して、今度は直接ROMカートリッジに拡張音源チップを搭載する形になりました。
当時のコナミは音楽に尋常ならざる力を入れていたので「少しでも良い音源で」「音源に最適化したアレンジで」というこだわりを感じます。
Bloody Tearsについて
今回演奏する「Bloody Tears」は昼間のフィールド曲(1面BGMに相当)で、本作のメインテーマと言える曲で、後のシリーズ作品にも度々登場して、多数のアレンジが存在します。
ニコ動界隈では「弾いてみた動画」の題材としても人気が高かった一曲です。
ドラキュラ2の音楽は、作曲者として松原健一さん、寺島里恵さん、村田幸史さんの3人がクレジットされています。
寺島里恵さんは前作も参加していて「Vampire Killer」の作曲者ですね。
「Bloody Tears」は松原健一さんの作ですので、今回は松原さんの紹介をさせていただきます。
作曲者の松原健一さん
松原健一さんは1986年から1994年頃にコナミ矩形波倶楽部に所属し「Taurus松原」「KEN」などのクレジットネームでコナミの作品の音楽を作っていました。
本作の他、夢大陸アドベンチャー、グラディウス2、悪魔城ドラキュラ(AC版)、ワイワイワールド2、コントラFORCE、ツインビー・レインボーベルアドベンチャーなどに参加。
コナミ退社後は一時期SCEでゲーム音楽を作っていました。
その中で、今回演奏の「Bloody Tears」は最も有名な曲だと思います。
以下、ソロギターアレンジに関して書いていきます。
オリジナルとPCE版をミックス【ソロギター演奏】
今回は、オリジナルのファミコンディスクシステム版とPCE版『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』に収録されているバージョンをミックスしてアレンジしました。
オリジナル版は1ループ30秒しかないので、PCE版の間奏を挟んで2ループの演奏にしています。
「Vampire Killer」の演奏の時もPCE版のアレンジを採り入れてサイズアップしたので、それに習ってやった感じです。PCE版「血の輪廻」のアレンジ好きなんですよねー。
キーはオリジナルがB♭マイナーキー、PCE版はDマイナーキーですが、このギターアレンジではAマイナーキーでアレンジして、1フレットにカポタストを付けてオリジナルのB♭マイナーキーにして演奏しました。
このアレンジは、左手のストレッチがキツいところもあるので、1カポだと少し楽になるという事情もあります。
では、曲の頭から順を追ってアレンジの解説をします。
イントロとアウトロのパイプオルガンぽいパートは、タッピングや高速アルペジオでも試してみましたが、難易度が上がる割には効果的でない感じなので、普通のトリルでアレンジ。
Aメロは細かく合いの手が入ったりしていて、全部弾こうと思うと結構難しいですが、ここは弾かないと再現度がかなり下がってしまうので、頑張って弾きました。
Bメロはもう1オクターブ下げれば楽なんですが、曲の盛り上がり部分だし、メロディーは高音で弾きたくてストレッチで頑張りました。
そしてPCE版から拝借した間奏部分は一応全部耳コピーはしましたが、ギターでの響きや弾きやすさを考えて多少意訳アレンジになっています。
間奏が終ってから、2ループ目に入るところで、またイントロと同じようなトリルパターンを入れてますが、ここはPCE版を参考に4度下から入っています。1ループ目と変化をつける意味でも、このほうが良いと思いました。
その後、もう1ループやって、イントロと同じパターンに繋いでエンディングとしました。
Bloody Tears(血の涙)コード進行
イントロ
|Am|E7|Am|E7|
Aメロ
|Am|G|F|E7|
|Am|G|F|E7|
Bメロ
|Am G|FM7 G|Am G|FM7 E7|
Cメロ(PCE版の間奏)
|Am|A7|Dm(onF)|B♭(onF)|
|Gm|E♭(onG)|C(onG)|F|
|F♯dim7|F♯dim7|E9sus4|E|
|Em|Em|Am|Am|
Aメロ繰り返し
Bメロ繰り返し
アウトロ(イントロと同じ)
|Am|E7|Am|E7|
|Amadd9|
コード進行分析
イントロ
■Aマイナー
|Ⅰm|Ⅴ7|Ⅰm|Ⅴ7|
Aメロ
|Ⅰm|♭Ⅶ|♭Ⅵ|Ⅴ7|
|Ⅰm|♭Ⅶ|♭Ⅵ|Ⅴ7|
Bメロ
|Ⅰm ♭Ⅶ|♭Ⅵ ♭Ⅶ|
|Ⅰm ♭Ⅶ|♭Ⅵ Ⅴ7|
Cメロ(PCE版の間奏)
|Ⅰm|Ⅰ7|
■Dマイナー(下属調)
|Ⅰm|♭Ⅵ|
■Gマイナー(下属調)
|Ⅰm※1|♭Ⅵ|Ⅳ|♭Ⅶ|
■Aマイナー
|Ⅵdim7※2|Ⅵdim7|Ⅴ7sus4|Ⅴ7|
Aメロ繰り返し
Bメロ繰り返し
アウトロ(イントロと同じ)
|Ⅰm|Ⅴ7|Ⅰm|Ⅴ7|
|Ⅰm|
※1 DマイナーキーのⅣmと共用
※2 Ⅱ7の代理。GマイナーキーのⅤ7と共用
間奏以外は凄くシンプル【コード進行のポイント】
オリジナルのAメロBメロ部分はシンプルなマイナー下降進行で、ほとんど何も言うことが無いくらいシンプルです。
ただし、メロディーや合いの手はテンションノートが多いので、運指は少しおぼえにくかったです。
コード進行的には、PCE版から引っぱってきた間奏部分が面白いです。
間奏部分は3つ目のDm(onF)か4つ目のB♭(onF)あたりから転調ぽくなっていますが、どこに転調してるのか?は複数の解釈が成立します。
Dm(onF)→B♭(onF)→Gm→E♭(onG)→C(onG)→F
ここの部分ですが、以下の可能性が考えられます。
Dマイナーキー
Ⅰm→♭Ⅵ→Ⅳm→♭Ⅱ(ナポリコードまたはⅤ7の裏コード)→♭Ⅶ→♭Ⅲ
Gマイナーキー
Ⅴm→♭Ⅲ→Ⅰm→♭Ⅵ→Ⅳ(SD)→♭Ⅶ
Cマイナーキー
Ⅱm(SD)→♭Ⅶ→Ⅴm→♭Ⅲ→Ⅰ7→Ⅳ(SD)
この3つはどれでも成立するし、複数回転調も考えるとかなりのパターンの組み合わせが考えられますが、自分はDマイナーキー→Gマイナーキーの流れが一番しっくりくると感じたので、それでアナライズしています。

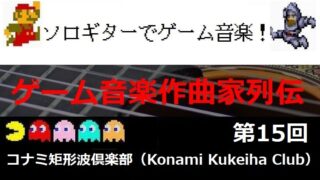
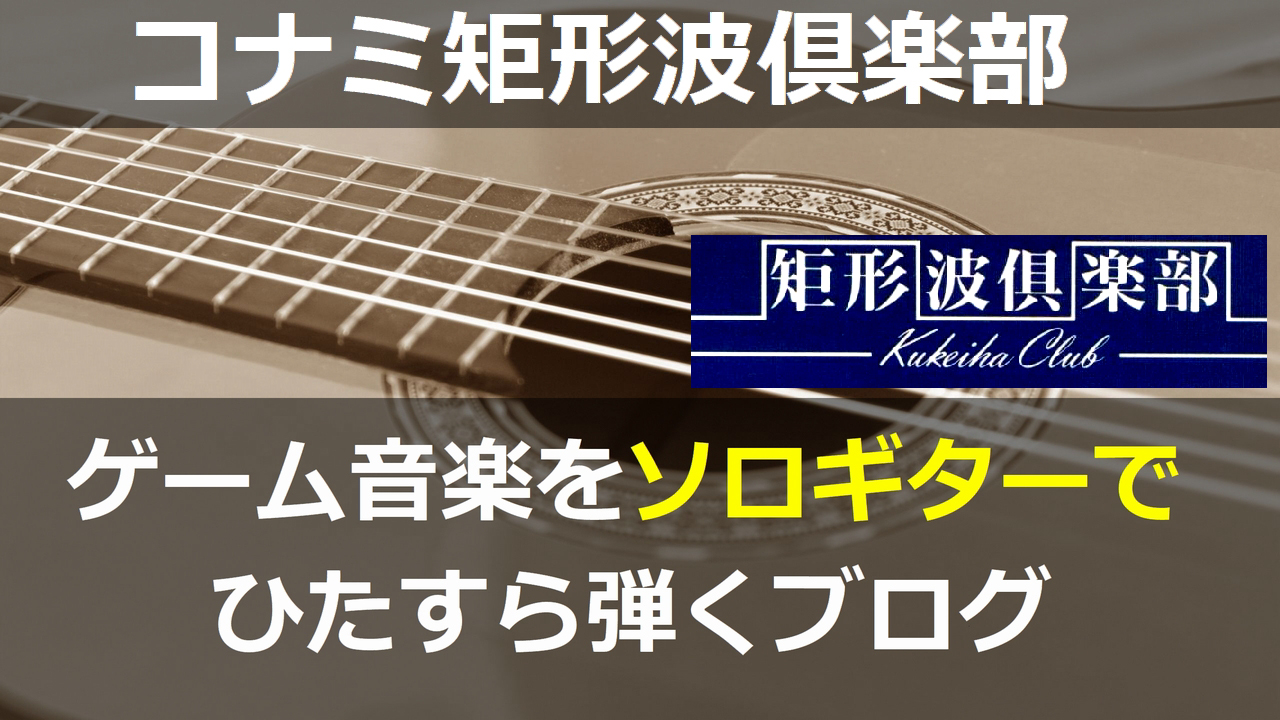
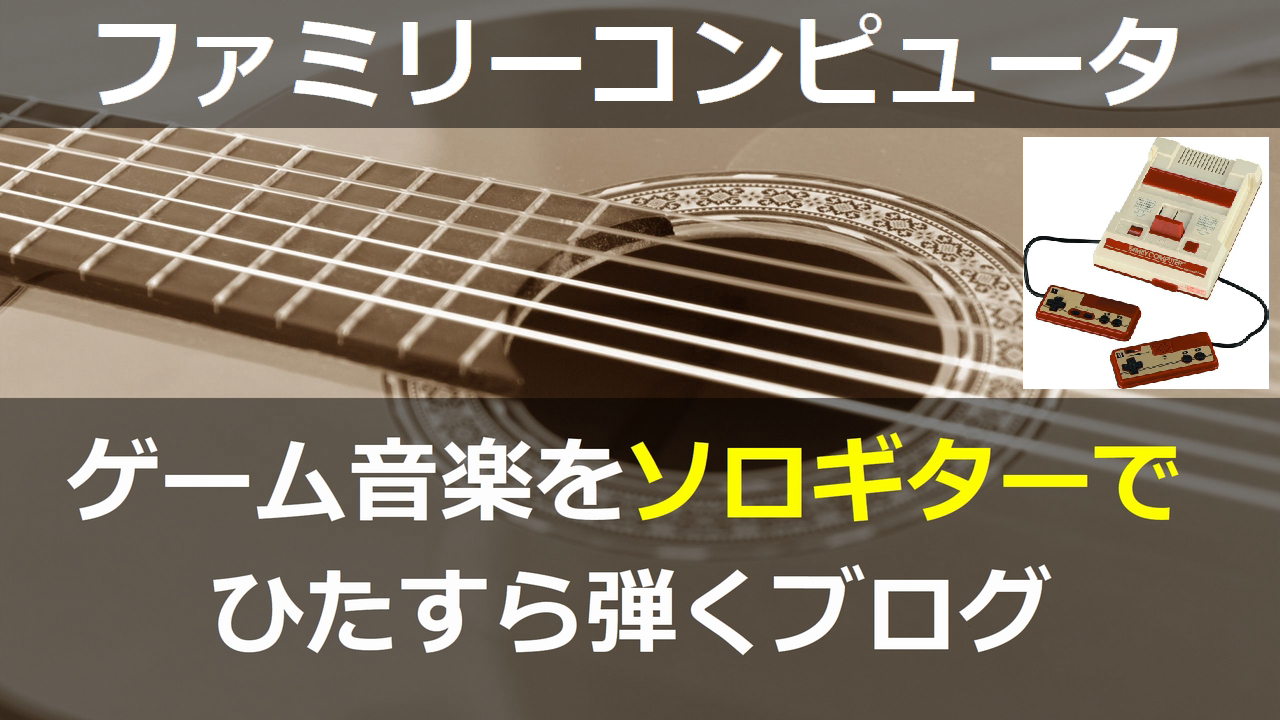
コメント