発売年月:2009年3月
機種:ニンテンドーDS(NintendoDS)
メーカー:セガ(SEGA)
タイトル名:セブンスドラゴン(7th DRAGON)
曲名:密林航行(Jungle Navigation)
作曲:古代祐三(Yuzo Koshiro)
演奏難易度:☆☆☆★★(易しい)
ゲーム音楽ソロギター演奏動画・コード進行解説の第38弾は、セブンスドラゴンより「密林航行」。
作曲は古代祐三さんで「ミレクーラ森林」や「美しきメイヘル」などの森林ステージで流れる静かなピアノ曲です。
セブンスドラゴン作品概要
セブンスドラゴン(7th DRAGON、通称ナナドラ)は2009年にセガから発売されたRPGで、音楽担当は古代祐三さん。
「世界樹の迷宮」との関連
セブンスドラゴンはいくつか続編も出ていますが、世界樹の迷宮シリーズ(アトラス)の兄弟作品といえます。
セブンスドラゴンシリーズは、世界樹の迷宮シリーズの初代プロデューサーである新納一哉氏が手掛けていて、両シリーズとも古典的なRPGに回帰したような作りになっているのが特徴。
古代祐三さんによるFM音源風音楽
音楽は「世界樹の迷宮」「セブンスドラゴン」両シリーズともに古代祐三さんが担当していて、FM音源時代からスーパーファミコン時代を彷彿とさせるようなサウンドになっています。
レトロゲーム音楽のリバイバル的な動き
セブンスドラゴン&世界樹の迷宮をはじめとして、この年代(2005年から2013年頃)、こういう作りのゲームが一定数出ていて結構売れているんですよね。
ゲーム第1世代だけでなく、もっと若い層にも受けているようです。
DS版の悪魔城シリーズ(コナミ)なんかも2Dグラフィックスに1980年代&1990年代ゲーム音楽風のサウンドということで共通しています。
PCの『洞窟物語』や、チップチューンの再ブームとも時期が被るので、一つの大きなトレンドだったんでしょう。
2Dのドット絵や、古典ゲームミュージックのリバイバルですね。
この流れは後のアンダーテールのヒットにも繋がっていっていると思うし、1ジャンルとして定着している感はありますよね。自分は大好きな路線です。
「密林航行」曲紹介
今回演奏する「密林航行」は「ミレクーラ森林」や「美しきメイヘル」などの森林ステージで流れる曲です。
セブンスドラゴンの音楽がレトロゲーム音楽風といっても、この曲「密林航行」は静かなピアノアレンジで、ピコピコガシャガシャした感じは皆無。
古代祐三さんの作風は、イケイケのガシャガシャした曲も得意ですが、以前ここで取りあげたイース「Feena」などの時代から、こういう静かな路線の曲も凄く良いですよね。
この曲はメロディーのとりかたがクラシック系ではなく、1980年代のフュ-ジョンやユーミンなどのちょっと洒落たニューミュージック風に感じます。
ちなみに続編のセブンスドラゴン2020では、渋谷のBGMとしてこの曲が再登場していますが、そちらはエレクトロ・アレンジですね。
シンプルなだけに丁寧に演奏【ソロギター演奏】
オリジナルはFマイナーキーですが、ソロギター用に半音下のEマイナーキーに移調しています。
Bメロは4回繰り返しですが、2回に短縮。
今回、アレンジ段階では「コードもシンプルだし、あまりガチガチに決めずに適当に弾いてサクッとアップしよう」なんて思っていたんですが、録り始めたら意外と大変でした。
このアレンジ、音がちゃんと出てない所とか、すごい目立つんですよね。
あと、表情付けとか強弱とかも気になりました。
弾くのでいっぱいいっぱいのアレンジだと気にする余裕無い事が、こういうシンプルなアレンジだと凄く気になるという。
1回撮り終えたんですが、なんだかダメダメだったので、少し練習に戻って2回戦。ですので、それなりに時間がかかりました。
密林航行 コード進行
オリジナルのFマイナーキーをEマイナーキーに移調しています。
イントロ
|CM7|D69sus4|Em|Em9|
|CM7|D69sus4|Em|Em|
|CM7|D|Em|Em9(onB)|
|CM7|D|Em|Em9(onB)|
|CM7|D69sus4|Em|Em9(onB)|
|CM7|D69sus4|Em|Em9(onB)|
|CM7|D|Em|Em9(onB)|
|CM7|D|Em|Em|
Aメロ
|CM7|CM7|Bm7|Bm7|
|CM7|CM7|Bm7|Bm7|
|Am7|Am7|Bm7|Bm7|
|Am7|Am7|Bm7|Bm7|
Aメロくり返し
Bメロ
|Esus4|Em|Esus4|Em11|
|Esus4|Em|Esus4|Em11|
|Esus4|Em|Esus4|Em11|
|Esus4|Em|Esus4|Em11|
コード進行分析
イントロ
■Eマイナー
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
|♭ⅥM7|♭Ⅶ|Ⅰm7|Ⅰm7|
Aメロ
|♭ⅥM7|♭ⅥM7|Ⅴm7|Ⅴm7|
|♭ⅥM7|♭ⅥM7|Ⅴm7|Ⅴm7|
|Ⅳm7|Ⅳm7|Ⅴm7|Ⅴm7|
|Ⅳm7|Ⅳm7|Ⅴm7|Ⅴm7|
Aメロ繰り返し
Bメロ
|Ⅰsus4|Ⅰm7|Ⅰsus4|Ⅰm7|
|Ⅰsus4|Ⅰm7|Ⅰsus4|Ⅰm7|
|Ⅰsus4|Ⅰm7|Ⅰsus4|Ⅰm7|
|Ⅰsus4|Ⅰm7|Ⅰsus4|Ⅰm7|
Bメロの音使いがキモ【コード進行のポイント】
この曲は、コード進行自体はシンプルなものですが、メロディーのとりかたが秀逸です。
この曲のキモであるBメロ=サビの部分ですが、Ⅴm上でP4→M6→m7の音が使われていますが、ここの音使いが非常に効いていて、この曲の要となっています。
こういう1フレーズで全て言い切ってしまうようなものって、凄いかっこいいですよねー。
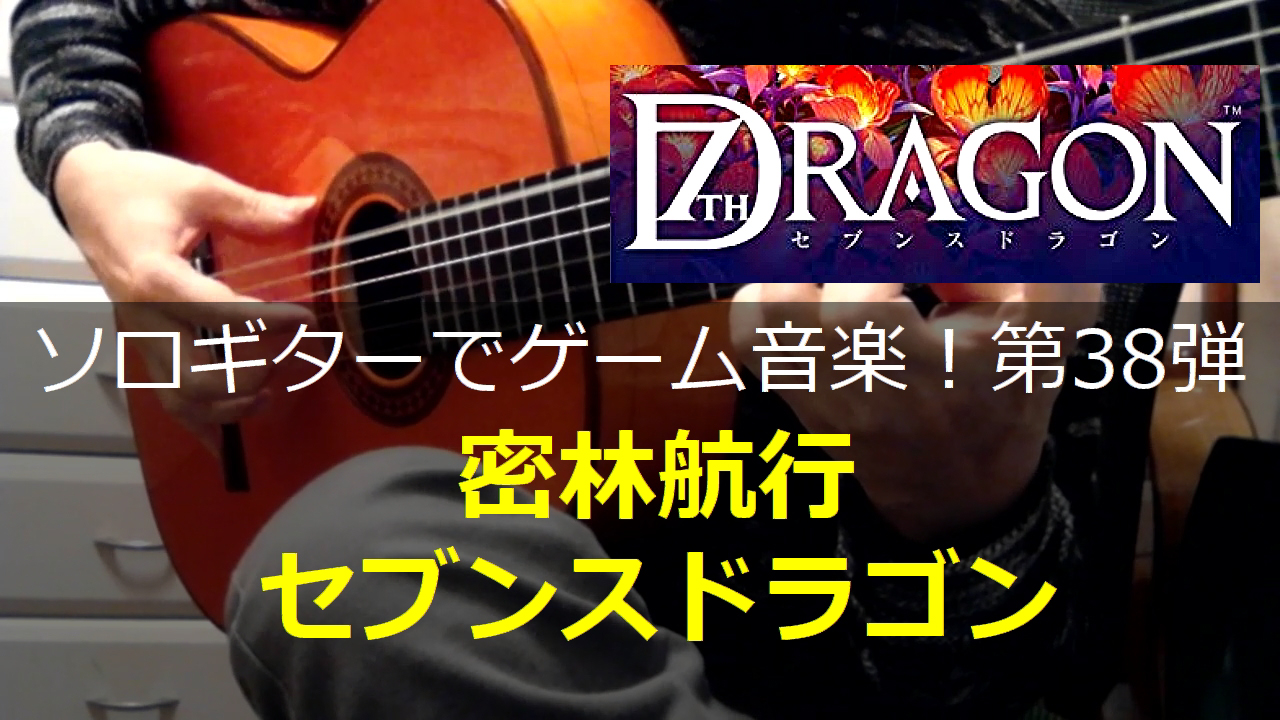

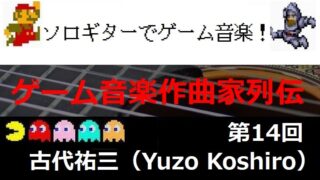



コメント