このブログ管理人=BGMは、今までいろんな音楽に触れ、影響を受けてきてますが、自分の音楽のルーツを辿っていくと、その源流は子供時代に親しんだ1980年代のゲーム音楽に行きつくことに気づきました。
もっと遡ると親が聴いてた音楽やTVから流れてくる歌謡曲や、アニメの主題歌ってことになるかもしれませんが、積極的に音楽に興味を持って「自分で演奏したい」「作りたい」と思った直接のキッカケはゲーム音楽だったように思います。
なにしろゲームのBGMは同じ旋律を延々とループして聴かされるわけだから影響も強烈だと思います。
この「改訂版ゲーム音楽の想い出」は、2019年秋から2020年の始めにかけて連載していた「ゲーム音楽の想い出」と、このブログ開設直後に公開した「自分とゲーム音楽の関わり」の内容を統合・再構成して時系列順にまとめたもので、今までの自分とゲーム音楽の関わりと、このブログ開設までのいきさつを書いています。
第1回は、自分BGMの幼少時代からファミコンを購入するあたり(ウチは1984年末でした)までの1980年代前半のことを中心にお話します。
この年代は、ビデオゲームの黎明期から発展期の入り口に当たりますが、当時のゲーム音楽周辺事情は「ゲーム音楽史」で詳しく書いていますので、ご一読いただければと思います。
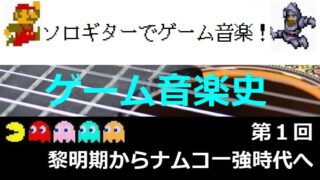
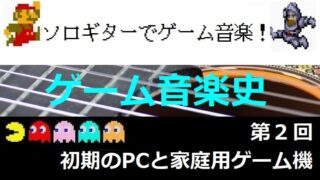
ボードゲームからビデオゲームへ
当ブログ管理人=BGMが幼少の頃は、ボードゲームがブームでした。
タカラの人生ゲームとか、その元ネタのモノポリーとか、バンダイのボードゲームシリーズとか、家族や友達とワイワイやっていましたよね。
1978年から1979年にスペースインベーダーブームがあり、新しいテクノロジーの台頭とともに、ゲームの主流もボードゲームからTVゲームへと徐々に移っていきます。
BGMがTVゲームに興味を持ち始めるのは1981年前後でしょうか。ファミコンが出る2年くらい前で、まだまだボードゲームブームが隆盛だった時期ですね。
当時はスペースインベーダーブームを受けてナムコを中心としたアーケードゲームが数多く出始めていました。
ゲームコーナーの思い出
良く思い出してみると、BGMが最初にビデオゲームに興味をもったキッカケは、幼少の頃に家族に連れて行ってもらっていたショッピングセンターや百貨店にあったゲームコーナーだと思います。
この時代の百貨店は屋上などにゲームコーナーがありましたよね。
ギャラガ・ポールポジションといったナムコ作品の記憶があるので、時期的には1981年から1982年頃の事と思います。
まだ自分で100円払ってゲームを出来る年齢ではなかったので、よその人がやるのを後ろから見ていただけでしたが、当時の先端技術を感じて、憧れの気持ちをもっていたのはおぼえています。
ゲーム&ウオッチとポータブル電子ゲーム
当時(1981年頃)は、家庭用ゲーム機といえば「ブロック崩し」(任天堂)でした。
当時は1家庭にTVは1台というのが普通で、TVゲームを繋いである家はまだ少なく、持っている家は子供の溜まり場になっていました。
当時はいろいろと大らかな時代でしたねー。
子供の資金力で買えるのはゲーム&ウオッチなどのLCDゲームやポータブル型の固定表示の電子ゲームで、友達と貸し借りしてやるのがデフォでしたよね。
ファミコンの普及以前は、ドット単位で動く、ゲーセンにあるようなビデオゲームは憧れの象徴でした。
トミーの電子ゲーム
BGMもご多分に漏れず、ゲーム&ウオッチなどを友達と貸し借りしてやっていたのですが、それと同時期、多分1981年の誕生日に買ってもらったものと思われますが、トミーから発売されたポータブルゲーム版のパックマンを持っていました。
色んなところにもっていって、ずーっと飽きずにやっていた記憶があります。
トミーがナムコにライセンス料を払って売っていたものと思いますが、かなり売れたみたいで、持っていた人も多いと思います。
でもこれって、アーケードゲームやテレビゲームのようにドット単位で動くものではなく、電光掲示板(?)のようなあらかじめ決まったパターンが操作に応じて光る、というものでしたが、効果音と簡単なメロディーが出ました。
ゲームコーナーで見ていたアーケードゲームを別にすると、メロディー付きのゲームサウンドに触れた体験はこれが初めてと思います。
今考えるとトミーの電子ゲームシリーズは、当時の安価なポータブルゲームとしては音もゲーム性も凄く良くできていたと思います。
そのあと、弟が同じトミーのケイブマンを買って、同じシリーズのスクランブル(オリジナルはコナミのアーケードゲーム)も持ってましたので、トミーの電子ゲームはかなりのお気に入りだったんだと思います。
友人宅にあったカセットビジョン
そんな時代でしたが、1982年の夏頃かな?(暑かった記憶があるのでたぶん夏頃)最新鋭のTVゲーム「カセットビジョン」(エポック社、1981年発売)を近所の友人宅が購入したので、その家に毎日のように押しかけてゲームに講じていました。
外で遊んだ帰りは、友達や弟と、必ずその家でゲームをやって帰る、みたいな迷惑な子供でしたが、その家のご両親も子供好きだったので、可愛がっていただきました。幸せな思い出です。
駄菓子屋のアーケードゲーム体験
自分が日常的にアーケードゲームに触れるキッカケになったのは、駄菓子屋通いでした。
駄菓子屋に設置してあったアーケードゲームを冷やかしはじめたのは1982年後半頃と思いますが、通っていた小学校の何軒か隣の駄菓子屋にあった、型落ち10円ゲームのムーンクレスタ(日本物産、1980年)が最初です。
そのあと1982年終わり頃から別の駄菓子屋にムーンパトロール(アイレム、1982年)が登場したので、それをやるために通いました。確か1ゲーム20円。
インベーダーブーム以降、地方の駄菓子屋でも子供向けに型落ちのアーケードゲームを設置しているところがたくさんあって、10円から50円でプレイできました。
1982年から1983年にかけて、下記のようなアーケードゲームを駄菓子屋で体験しました。
- パックマン
- ニューラリーX
- ボスコニアン
- ディグダグ
- ギャラガ
- ドンキーコング
- バーニンラバー
今考えると、発売後半年から1年経つと駄菓子屋に型落ち基板が回ってきて、子供向けに安く提供していた、という感じですかね。
ファミコン発売
1983年7月に任天堂からファミリーコンピューターが発売されます。
BGMがはじめてファミコンに触れたのは1983年の8月頃でしょうか。確か夏休み中でしたので。
地元のデパートのオモチャ売り場にゲーム機展示コーナーが出来て、ファミコンをさわることができたんですよね。
まだドンキーコング、ドンキーコングJr、ポパイの3種しかソフトが無くて、その後すぐにマリオブラザーズが発売されたタイミングです。
それまで、TVゲームというと「ブロック崩し」か、カセットビジョンしか無かったし、アーケードゲームはまた全然別世界のモノだったので、ファミコンの登場には、かなりの衝撃を受けました。
しかも14800円という、お年玉を貯めれば買えそうな額です。
でも、BGMはその時はPCに興味が傾いてきていて、ファミコンはすぐには買いませんでした。
ちなみに、友達が何人かファミコンを買ったので、そこに遊びに行ってやっていました。皆でやるほうが楽しかったし。
この当時は、まだRPGなどの純粋に一人でやるゲームはあまり普及しておらず、アクションゲームを友達や家族と一緒にやる場合が多かったように思います。
マイコン大百科
自分の家は両親が本を読むのが好きだったので、月に何回か家族で大きな書店に出かけていて、その時子供も何か一冊本を買ってもらえました。
1983年秋から冬頃だったと思いますが「マイコン大百科」(自分が最初に入手したのは実用編。ケイブンシャ、1983年)という本を買って貰ってPCの世界を知りました。
その本にはアメリカのAppleⅡのロールプレイングゲームやアドベンチャーゲームの画面写真も載っていて(それは少し後に買ったゲーム編のほうだったかも)「アメリカにはこんな凄いものがあるんだ」と憧れていました。
その本では、ゲームの画面写真のみならず、PCの基礎知識やBASICプログラムの初歩まで解説していて、飽きずに何度も読んでいました。
当時の自分にとってはPCは未来を象徴する夢の機械で「BASICプログラムさえおぼえれば何でもできる」みたいに思っていました。
こんな感じで1983年後半、ファミコン発売とマイコン大百科を入手したのが重なって、自分の中でTVゲーム・コンピューターへの興味が一気に加熱ていきます。
駄菓子屋にゼビウス登場!
1983年の終わり頃だったと記憶していますが、ついにゼビウス(ナムコ、1983年1月稼働開始)が近所の駄菓子屋に登場します。
ゼビウスは自分にとって衝撃的な作品で、今考えても、あの時代にあれを出したいうのは本当に凄いことだし、一級の芸術作品じゃないでしょうか。
当時触り始めていたファミコンのゲームも衝撃でしたが、ゼビウスのリアルな世界観と美麗なグラフィックスは全く次元の違うものに感じました。
BGMはゼビウスの世界に夢中になり、かなりのお小遣いを注ぎ込みました。1984年前半は駄菓子屋でゼビウスばかりやってたと思います。
家電展示場のMSX
BGMが住んでいた地元に大きな家電展示場がありました。
1983年末から1984年初頭くらいだったと思いますが、そこにある日、MSXが大量に展示されて(20台くらいあったかな?)自由に触ることができるようになったんですよね。
ゲームカートリッジも沢山用意されていました。
周辺の子供のコミュニティーで「タダで色んなゲームが遊べる所がある」と噂になり、近所の子供が押し寄せることになります。
BGMもしょっちゅう行っていましたが、いつもチャリが道にはみ出すほど大量に停まっていましたね(笑)
MSXの魅力
1983年の6月に策定されたMSX規格ですが、これはPC市場で出遅れた家電各社が連合して統一規格の安価なPCを投入して巻き返しを図ろうというもので、米マイクロソフト社も巻き込んだ大掛かりなものでした。
この規格の中心になったのはソニーと松下電気でした。
ファミコンの登場によって危機感を募らせた家電各社は発売を前倒しして、1983年10月から12月頃には主要メーカーのMSX機が出揃ってきます。
BGMは「マイコン大百科」を読んで以降、PCに並々ならぬ興味をもっていましたが、当時のPCは高価でサラリーマンの月給以上の値段がしてました。
でも、BGMはファミコンよりも、いかにも「コンピューター」という感じのキーボードがついてる知的な機械=マイコンに惹かれていました。
そういうタイミングで家電展示場に登場したのがMSXです。
- PCとして最低限の機能は備えている
- TVに繋いで出来るのでモニターを買わなくていい
- カートリッジ式のゲームソフトが使えてファミコン感覚のゲーム機として使うこともできる
- 安い。出始めの時でも5万円くらいから、しばらくすると2万円台のものも登場
- MSX向けにナムコやコナミのアーケードゲーム移植シリーズが出始めた(ファミコンより早かった)
こんな条件が揃って、家電展示場でMSXを触っていたBGMはMSXが欲しくてたまらなくなりますが、子供にとってかなり高額な買い物だったし、実際に購入するのは1984年秋頃の話です。
マイコンBASICマガジン
「マイコン大百科」を読んでPCに興味津々だったBGMですが、家族で行っていた書店の雑誌コーナーにPC関連の雑誌が置いてあるのに気がつき、ずっと気になっていました。
でも、そういう雑誌は「大人向け」の認識があったのか、なかなか買うまでいかなかったんですが、ついに、そのうち一冊「マイコンBASICマガジン1984年7月号」を手に取ります。
それはX1版のゼビウスの特集が付録でついていて、それに引き寄せられました。
実際に読んでみると、毎月BASICで作られたゲームが大量に投稿されていて、それを読んでいるうちにPCゲームやBASICプログラミングへの興味が一気に高り、毎月購読するようになります。
マイコンBASICマガジン=ベーマガはゲーム関連の記事や広告が多く、PCのアドベンチャーゲーム攻略記事や新作アーケードゲームの紹介、巻末には全国のゲーセンのハイスコアランキングなどが掲載されていました。
当時、PC雑誌はベーマガの他にログイン、ポプコムなどがありましたが、それらも買うようになりました。
月刊マイコンとか、月刊I/Oとか、電話帳みたいな厚さのもありましたねー。
電話帳系の雑誌には長大なマシン語ダンプリストとか載っていましたが、あんなん打ち込める人いるのかな?と思ってました。
ベーマガの1、2ページのBASICのリストですら、打ち込んでデバッグするのに2、3時間はかかってましたから。
ゲーセンデビュー
ベーマガでは新作のアーケードゲームの紹介もされていました。
その中でも凄くやりたかったのがドルアーガの搭(ナムコ、1984年)です。
でも、新作ゲームは駄菓子屋では出来ないので、ゲームセンター(以下ゲーセン)に行く必要があります。
当時はゲーセンが近くになかったうえ「不良のたまり場」みたいなイメージでした。
実際に、薄暗いスペースで目つきがおかしいお兄さんがたむろしていて、うっかり足を踏み入れると即カツアゲされそうな場所ではありました。
実際、ゲーセンで何回か絡まれております(笑)
近所に新しいゲーセンができた!
当時はそんな感じでゲーセンは子供には敷居の高い場所でしたが、1984年の夏休み前くらいだったと思いますが、近所に新しくゲーセンがオープンしました。
友達と何回か偵察に行きましたが、わりと明るい店内でヤンキーもまだ出入りしておらず、子供でも入りやすい感じでした。
目的はドルアーガの塔でしたが、通い始めたときにはすでに新作のパックランド(ナムコ、1984年)、ソンソン(カプコン、1984年)などが並んでいた記憶があります。
ただ、そのゲーセンは100円だったんですよねー。
なので、やるときは失敗は許されず、ベーマガなどの攻略情報を熟読して臨みました。
あとはたまに上手い人が来ると観戦する人だかりが出来たり。自分もゲーセンにいる時間はほぼ観戦でしたが。
当時はアーケードゲームが上手いのは仲間内でもかなりのステータスだったので、自分も上手くなりたくてテクニックや攻略を研究しました。
このゲーセンでは、ドルアーガの塔、パックランドに始まり、スターフォース(テクモ、1984年)、1942(カプコン、1984年)、ドラゴンバスター(ナムコ、1985年)、イーアルカンフー(コナミ、1985年)などをプレイしていました。
ゲームの稼働時期を考えると、このゲーセンに出入してたのは1984年の夏から1985年の春先くらいまでですね。
そして、やっとゲーム音楽の話題ですが、自分がゲーム音楽を「音楽」として認識したのは、このゲーセンでやったドルアーガの塔、パックランド、ソンソン、エレベーターアクション(タイトー、1983年)あたりが最初と思います。
その時点(1984年頃)では、まだゲーム音楽にも音楽自体にも、それほど興味があったわけではなく「アーケードゲームの音楽は豪華だなぁ、聴いてて気持ちいいなぁ、テンション上がるなぁ」というくらいでしたが。
MSXを購入
ベーマガを購読するようになってから、色んな新しい情報を得て、PCがどうしても欲しくなり、1984年の秋頃、ついにMSXを購入しました。
家のテレビを弟と2人で占拠してベーマガとかMSXマガジンのダンプリストを打ち込んだりしていました。
MSXのゲームはナムコのアーケード移植シリーズや、カセットテープ版のアドベンチャーゲームをやっていました。
ムー大陸の謎(マジカルZOO、1983年)とか、デゼニランド(ハドソン、1983年。MSX版は青白画面!)とか。
専用のデータレコーダでない普通のラジカセでもなんとか行けましたね。
MSXでやった初期のPCゲームの音楽で一番記憶に残っているのは、ボコスカウォーズ(アスキー、1983年)のテーマです。
「進めー、進めー、者どーもー」ていう歌詞がついてたアレです。知らないか(笑)
そうしてしばらくMSXをで遊んでいたのですが、ベーマガなどのPC雑誌を読んでPCゲームの最新トレンドを知ってしまうと、すぐにMSXでは物足りなくなって来るわけですね。
ファミコン購入
1984年当時、自分の興味の中心は次々と刺激的な作品が登場するアーケードゲームと、アドベンチャー・シミュレーション・RPGなどの最先端の知的な遊びを生み出しつつあったPCゲームでしたので、ファミコンが普及していくのを横目でみながら、購入には至っていませんでした。
しかし、1984年11月にファミコン版のゼビウスが発売されると、急激にファミコンが欲しくなってきます。
当時はベーマガ購読の切っ掛けとなったX1版ゼビウスが移植版ゼビウスの中では最高峰でしたが、ファミコン版のほうがX1版より出来が良かったんですね。
この一年くらい前から駄菓子屋でゼビウスをプレイしはじめたBGMですが、ついに憧れのゲームを家にで出来るようになるわけです。
こういう理由でゼビウスをやるためにファミコンを1984年の末あたりに購入しました。
それ以降、アクションゲームは主にファミコンでやるようになります。
ファミコンのソフトは、友達と貸し借りしながら、1986年頃までの主要タイトルはほとんどやっていたんではないでしょうか。
――次回はBGMがゲーム音楽にはまるのと同時に、音楽そのものに興味を持って楽器なんかを始めるあたりの体験談です。
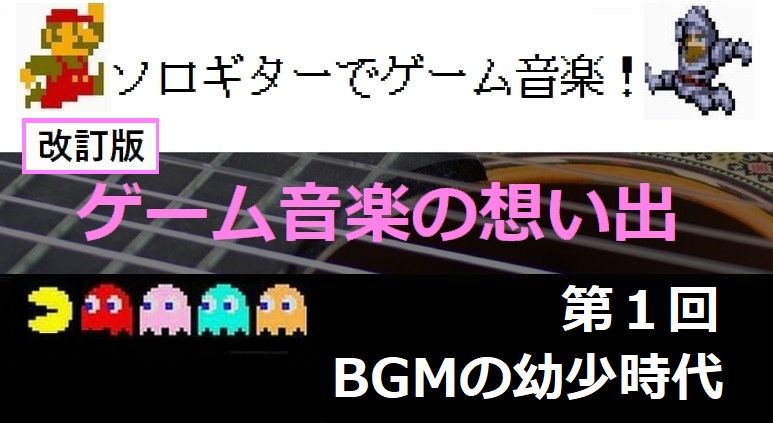
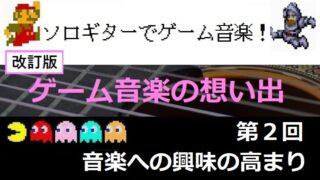
コメント