ゲーム音楽史では前回、黎明期から「ナムコ一強時代」についてお話しましたが、1980年から1984年頃までのゲーム音楽は、ナムコを中心としたアーケードゲームが圧倒的なリードをしていました。
ですが、その裏では国産のPCや家庭用ゲーム機の業界が形成されつつありました。
今回は黎明期のPCと、ファミコン登場以前の家庭用ゲーム機(コンシューマー機)のゲーム音楽事情をみていきます。
まずは、「マイコン」と呼ばれていた初期のPCについてです。
AppleⅡの発売
1977年にアメリカで「AppleⅡ」が発売されました。
これには一応サウンド機能が備わっていたらしいのですが、後に拡張用のPSGカードが出ているので、初代のはBEEP音の音程を変えられるタイプでしょうか。すみません、AppleⅡのハードはあまり詳しくありません。
家庭用のゲームに関しては、このAppleⅡと、Atari2600(1977年発売のゲーム機、記事の後半を参照)のソフトが1980年代に入る以前から相当数出回っていて、この時代はまだアメリカが圧倒的に進んでいました。
国産初のPC
国産のPCは1978年発売のMB-6880(日立)、MZ-80K(SHARP)の2機種が最初です。
1979年にはNECからPC-8001が発売されベストセラーとなり、NECは国産PCのトップメーカーになりました。
しかし、この時代のPCはまだPSGも搭載しておらず、音楽を奏でるには程遠い状態でした。
PC-6001と「御三家」
1981年にNECから発売されたPC-6001にPSGがはじめて搭載されましたが、売れ筋は同時に出たPC-8801でした。こちらはビジネス向きでPSGを搭載していませんでした。
PC-6001は今思うと低価格で革新的な機能を備えたPCでしたが、グラフィックの解像度が低かったために、ゲームなどのホビー用途としてもあまり評価されなかったように思います。
翌1982年にFM-7(富士通)とX1(SHARP)というPSG搭載のホビー機が発売され大ヒット、PC-8801とともに「御三家」と呼ばれていました。
御三家に共通していたのは640×200ドットのカラー表示が可能で、細かいグラフィックやテキスト表示が要求されるRPG、シミュレーション、アドベンチャーなどのジャンルのゲームに適していたことです。
初期のPCゲーム業界事情
PC6001から御三家あたりが国産PCのゲーム音楽の夜明けと言って良いですが、なにしろハードも貧弱だし音楽を作るスタッフもいません。
国産ゲームソフト業界は立ち上がったばかりで、資金もなければ人材もいない状態です。
ゲームメーカーはほとんどがベンチャー企業で、プログラマーも不足していたため、プログラムコンテストなどを開催してアマチュアから人材を集めていた、そんな時代でした。
当然のことながら、音楽の質もナムコなどのアーケードゲームとは比べるべくもなかったです。
その後1983年10月頃からMSXが発売され、PCも低価格で買えるようになりましたが、しばらくは同じような環境が続いていました。
国産PCの奏でる音楽がそれなりのレベルに達して、アーケードゲームと肩を並べられるくらいになるのは1985年発売のPC-8801mkⅡSRの登場を待たねばなりません。
初期の家庭用ゲーム機
ここまでで、初期の8ビットPCのゲーム音楽事情をみてきましたが、後半はファミコン発売までの家庭用ゲーム機のゲーム音楽事情をお話します。
Atari2600
1977年にアメリカAtari社がカートリッジ式ゲーム機、Atari2600を発売して大ヒットしました。
Atari2600にはパルス1音+ノイズ1音というサウンド機能が備わっていました。サウンド機能は後述のカセットビジョンと同等でしょうか。
同時期のAppleⅡといい、当時のアメリカは日本より3、4年は進んでいた感じです。
ちなみに、自分はこれが世界初のカートリッジ式ゲーム機と思っていましたが、世界初はチャンネルF(1976年、フェアチャイルド)です。
カラーテレビゲーム15
Atari2600と同時期の1977年に、日本では任天堂がカラーテレビゲーム15を発売しています。
これの単機能版の「ブロック崩し」(1979年発売)が友人宅にあって、よく遊びに行っていました。
これらは単音の効果音が出せる程度のサウンド機能で、まだ音楽は無理でした。
カセットビジョン
1981年にエポック社からカートリッジ式のカセットビジョンが発売されます。
これは単音メロディ+効果音が出せました。このあたりでサウンド機能はようやくアメリカのAtari2600に追いついた感じです。
グラフィックはドットが粗すぎてなんともシュールな感じでしたが。
これまた友人宅で遊んでいたのですが、きこりの与作の「ヘイヘイホー、ヘイヘイホー」は憶えています。
ゲーム&ウオッチやポータブルゲームの流行
このあたりの時代、まだTVゲームは機能のわりに高価で、持っている家庭はごく一部でした。
代替品として子供の間ではゲーム&ウオッチに代表されるポータブル型の単機能ゲームが流行していました。
こうしたポータブルゲームも簡易的なメロディーを奏でる音源回路とスピーカーを内臓していたものが多く、そのメロディーが記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
ゲーム&ウオッチに関しては、そのコンセプトの通り「多少音階がついたアラーム音」という感じでしたが。
自分もゲームウオッチ他のLCDゲーム数種類と、トミーのパックマンなどの電子ゲームを持っていました。
ぴゅう太・ゲームパソコン
「日本で初めてのPSG搭載のゲーム機」というのを考えてみたんですが、一つの候補はトミーから1982年8月に発売された「ぴゅう太」でしょうか。
最近調べていて知ったんですが、「ぴゅう太」はBIOSからPSGがコントロールできるようですね。
このあと11月に、タカラ「ゲームパソコン」(=ソードM5のOEM製品)が出ていますが、これはナムコのアーケードゲームの移植タイトルが売りでした。
当ブログではMSX・MSX2をPCに入れていますが、ぴゅう太やゲームパソコンをコンシューマー機に入れるかPCに入れるかは微妙なところで、「ぴゅう太」が国産初のPSG搭載コンシューマーゲーム機である、というのは意見が分かれるところと思います。
これらの、いわゆるホームコンピュータ・ゲームパソコンなどと呼ばれるものは、主に玩具メーカーが製造して、他にも何機種か発売されていますが、ゲーム機としては値段が高く、PCとしては機能が弱かったのでファミコンやMSXが出回るとユーザーはそちらに流れてしまいました。
アタリショック
1982年から1983年頃にかけて、アメリカではいわゆる「アタリショック」が起きています。
これについて簡単に説明すると、Atari2600からのTVゲームブームに様々なメーカーが新規参入して質の低いゲームソフトを乱造した結果、ユーザーのゲーム離れが起きて、アメリカのゲーム業界全体が低迷するという事態になりました。
ただ、この年代、日本にはまだそんなに大規模な市場は無かったし、日本のゲーム業界への影響は軽微だったと思います。
この後、1985年にファミコンがNESとして欧米展開すると、これが大ヒットしてアメリカのゲーム業界復興のきっかけになっており、これ以降、日本のビデオゲームカルチャーは世界中に認知され、多くのファンを獲得していくこととなりました。
ファミコンの登場
1983年7月15日、ファミリーコンピュータ(任天堂)と、SC-3000・SG-1000(セガ)が発売されます。この3機種は発売日が同じでした。
「PSG搭載の国産コンシューマー機」と言い切れるのは、これらが初でしょうか。
この時期、他にもいくつかのゲーム機やゲームパソコンが発売されていますが、その中で画面表示機能に優れるファミリーコンピュータが主導権を握ることとなります。
ファミコンのPSGはカスタムチップが使用されていて、当時主流のものより音源性能も少し上でした。
以降、多くの人が知っている「ファミコンの歴史」がスタートするのですが、初期のファミコンソフト業界も、8ビットPCのゲーム業界と同じような黎明期の状況でした。
初期のファミコンのゲーム音楽については、アーケード移植ものは別にして、ご本尊の任天堂は音楽にはまだ本腰を入れていなかったし、他メーカーはまだまだ開発力・資金力が乏しかったため、ゲーム音楽も同時期のPCのものと似たり寄ったりのレベルでした。
ゲーム自体は任天堂製のものは非常にクオリティが高かったと思いますが、ファミコン独自のゲーム音楽の発展は、1985年のスーパーマリオブラザーズあたりからですね。
――このように、1984年頃までは、まだ日本の家庭用ゲームやPCゲームの業界は立ち上がりの時期で、音楽の質もナムコを筆頭とするアーケードゲームに太刀打ちできるものではありませんでした。
今回までで黎明期のゲーム音楽の周辺状況を解説しましたが、次回は変革の年である1985年に至るまでをお話しようと思います!
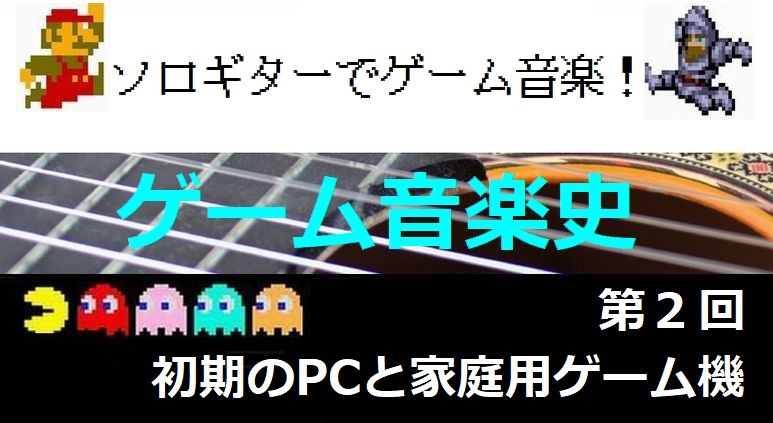
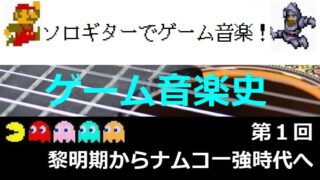
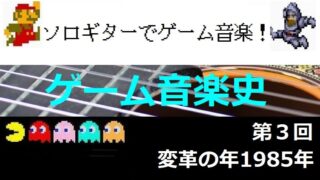
コメント