「ゲーム音楽を弾こう!」では前回までで採譜やコード分析といったことを中心にやってきました。
今回はソロギターアレンジの全手順を一気に解説しますが、今までやったことを総動員して1曲を鑑賞に耐えるクオリティーまで仕上げていきます。
コードの採譜と分析がある程度できているという前提ですすめます。
叩き台の仮アレンジを作る
アレンジの手順としては、まず叩き台の仮組アレンジを作るんですが、この連載の第2回講座でやったように、まずベース(できればルート音)とメロディで大雑把に仮アレンジしていきます。
ベースラインの決め方
コード進行のルートをベースラインにもってくるのが基本ですが、原曲がルート以外でベースを出していて、その音でないとイメージが変わってしまう場合は原曲のベースラインを優先してオンコードにして弾きます。
ベースが動いていて、それが曲の重要な要素になってる場合も極力原曲のベースラインを尊重します。
そしてベースラインを弾きながら、メロディが弾けるようなポジションを考えるのは「ゲーム音楽を弾こう!第2回講座」(上のリンク参照)で解説した通り。
コードフォームを決める
次にコードフォームを決めますが、以下の5つの条件で考えます。
- スムーズにメロディを弾けるか?
- ベースが維持できるか?
- 解放弦は使えるか?使えるなら使う
- コードとして必要な音が入れられるか?
- 前後のフレーズと上手く繋がるか?
自分の場合は「極力ベース音を維持したい」という考えがあるので、自然とコードフォームもそれに特化していきます。
具体的には、自分の場合セーハフォームが多くなってると思いますが、このへんもその人のスタイルで変わってくるものですよね。
セーハフォーム
セーハフォームは人差し指でベース音をおさえるのと同時に、何本かいっぺんに弦をおさえます。そしてそのままコードとスケールを弾きます。
セーハフォームはアコギで綺麗に鳴らすには慣れが必要ですが、ベース音を伸ばしながらメロとコードを弾くのに適しています。
また、コードトーンとスケールの把握もしやすいので(自分はそう感じます)、アレンジや暗譜が楽になるというメリットも。
中指ベースのフォーム
中指でベース音を押さえるタイプのコードフォームは指の形的にセーハフォームより押さえやすく、素早いコードチェンジに適しています。
ただし押さえながらのメロディ弾きはセーハフォームのほうがやりやすい場合が多いので一長一短かと。
セーハフォームからベースを半音か一音上げて中指ベースに移行する形もあります。
薬指・小指でベースを押さえるフォーム
メロディとベースの音域が接近している、いわゆるクローズドボイシングのときに、このフォームを使うことが多いです。
半セーハとの組み合わせになることもあります。
欠点は、このフォームだとベースを維持したままメロディを弾いていくのは、演奏難易度が高くなりがちということでしょうか。
オープンコードフォーム
解放弦を使って3フレットか4フレットくらいまでで弾けるコードフォームです。
解放弦を生かせる分、指が空くので自由度が上がります。
オープンコードフォームをいかに使うか?がソロギターアレンジの一つの大きなポイントじゃないでしょうか。
難しい部分にオープンコードフォームを使用できるように移調する、というのは非常に有効な選択肢になります。
ハイコード+解放弦
これも広い意味でオープンコードの一種です。
メロディを弾く都合でハイポジションでのコードフォームになることがありますが、このときベース音に解放弦が使えれば、ベース音をおさえなくてもよくなるので難易度が下げられます。
また、メロディとベースの音程差を大きくとれるので立体感を出せたり。
オープンコードフォーム同様に、これも活用できるように移調を検討するといいでしょう。
綺麗な音で鳴るフォームを考える
わざわざギターというソロ演奏が難しい楽器を使う、という理由を考えると、「音色」という要素は相当重要です。
アコースティックギターという楽器は、タッチのしかたで全く音色がちがってくるので、そのへんが醍醐味でもあります。
コードフォームや右手の弾きかたを考える際も、いかにいい音色で鳴らせるか?というのはかなり重要な要素になります。
例えば、音色の面で解放弦ではないほうがマッチすることも多く、そういう場合は敢えて解放弦を使用しない選択肢をしたり。
このように、アレンジの利便性・演奏性・音色といった事を考慮してコードフォームを決めて、一通り演奏可能な叩き台アレンジを作っていきますが、なかなか上手くいかない場合も多いので、次にそのあたりを解説していきます。
アレンジが行き詰まる原因
「一通り演奏可能な仮アレンジ」まで行きつけない、というのは、いろいろ原因はあると思いますが、「弾きたい音が決められてない」というような内容的なことを除外すると、ほぼ以下の2つに集約されてきます。
- ギターと音域がマッチしていない
- 演奏難易度が高すぎる
以下、これらの問題を解消する方法を考えてみましょう。
移調の検討
ギターに音域があっていなくて指板が広く使えないとアレンジが行き詰まりやすいので、こういう場合、思いきって移調を検討します。
移調先の決め方
どのキーに移調したら良いか?ですが、自分は以下の2点を基準に考えます。
- 曲の音域
曲中の最高音で出したい部分を基準に考えます。 - 演奏性
よく使うベース音に解放弦が使えればいろいろ楽です。あとは曲中で一番難所と思われる部分を上手く弾けるか?で決めます。
使用可能な解放弦を増やす
キールートが1フレットのキー(F、B♭、E♭など)の場合、半音下に移調すると解放弦が活用できて難易度が下がる場合が多いです。
ギターの場合は、こうした移調を活用するので必然的にA、Am、E、Em、Bm、D、Dm、G、Cなどのキーが多くなります。
カポタストの使用と半音下げチューニング
移調後でもカポタストを使えば、指使いを変えずにオリジナルキーで演奏することが可能な場合があります。
例えば、B♭メジャーキーの曲をAメジャーキーに移調した場合、1フレットにカポタストを付ければオリジナルのB♭メジャーキーに戻すことが可能です。
逆に、半音上に移調した場合は半音下げチューニングでオリジナルキーに戻すことができます。
例えば、A♭メジャーキーの曲をAメジャーキーに移調した場合は半音下げチューニングでA♭メジャーキーに戻すことが可能です。
オリジナルキーと演奏性を両立したい場合は、こうやって調整してやるわけです。
ちなみに当ブログのアレンジはソロ演奏だしオリジナルキーには拘らないので、原則、カポタストは使いません。
カポタストをつけると、その分指板が狭くなりますし。
コードボイシングの変更
移調してキーをギターに最適化しても、まだ弾きづらいところがあるかもしれません。
そういう所は、だいたいメロディとベースの動きの関係で難しくなっているはずです。次はこれを解消しましょう。
調性の次はベースラインとコードボイシングを検討します。
ベースラインの再考
ベースラインの跳躍が大きかったりで弾きにくい場合、ベース音を組み換えます。
メロディとベースが近接して弾きにくくなる所もよく出てきますが、その場合はメロディーを変えるより、ベースをさらに低い音に変えれないか考えます。
ベース音の変更は「ルートが無理なら3度音」というのが基本ですが、5度音・7度音も実際にやってみて違和感がなければ検討します。
ドミナント7thコードは、むしろ積極的にベース音を3度とか7度に変えたほうがドミナント感が強まって良いかもしれません。
コードの省略
メロディーを弾きながらだと、コードの音が全部出せない場合もあるので、そういう箇所があった場合、以下の順番でコードの省略を検討します。
- コードの音を減らす
例えば1弦でメロディー、6弦でベースを出している場合、4弦と5弦は省略して指をメロディーに回します。メロディーと近接したコードトーンは綺麗に響くし、メロディーに織り混ぜやすいのでなるべく残して低音側のコードトーンから省略していきます。 - メロディーとベースだけにする
それでも難しい場合は、メロディーとベースの2音だけにします。 - メロディーのみにする
さらに技巧ギリギリのところや意図的にベース音を出したくないところはベース音もカットします。
メロディーの変更
メロディーの変更は原曲イメージを大きく変えてしまう場合があるので慎重に検討すべきですが、これがどうしても必要になってくるケースもあります。
メロディーを部分的に1オクターブずらす
ソロギターでメロディーに使える音域は、ベースを同時に弾く事を考慮するとせいぜい2オクターブ半くらいです。
原曲のメロディーの中でギターの音域で弾き切れない所は部分的にオクターブ上げたり下げることを考えます。
ギターの楽器特性上、オクターブ変更は避けられないことも多いですが、なるべく自然な流れになるように工夫します。
メロディーラインの変更
出来たらやりたくはない事と思いますが、難易度的に演奏するのが到底無理な場合は、メロディーライン変更も検討します。
ただし、これは作曲部分の変更になるので難易度が高いアレンジです。
原曲の雰囲気を残しつつ、演奏可能な程度まで難易度を下げる、というのは経験とセンスが必要ですので。
仮アレンジを肉付けする
ここまでは一通り演奏可能な仮アレンジの作りかたを学習してきましたが、ここからは「仮アレンジを演奏・観賞に耐えるものにするために肉付けしていく」ということをやっていきます。
仮アレンジの状態だと、基本は最高音にメロディー、最低音にベースが来るようにして、小節の頭でベースを出していると思います。
でも、そこから工夫しないと、どうしても単調になりがちですので、それを解消するため、いくつか肉付けのテクニックを挙げてみます。
1セクション丸ごと違う表現に
仮アレンジはメロディ+ベースを主体に作りますが、大きな変化をつけたい場合、1セクション丸ごと違う表現に変えたりします。
- アルペジオ主体にする
- トレモロにする
- 親指だけで弾いてみる
- リズムプレイに変える
- その他特殊奏法でやる
などなど、いろいろ考えられますが、各自得意な弾き方をいかせるように考えます。
次に、1セクション丸ごとではなく通常のメロディー弾きに絡めたりするような、細かい肉付けのテクニックを挙げてみます。
ベースラインを変化させる
ベースラインを少し変えてやることで大きな効果を出せることも多いですが、自分はこんな手法でやっています。
- ベースラインに動きを付ける
ベースに導入音を付けたり、次のベース音に向かってスケールや半音で繋いだり、他のコードトーンも入れてベース音をアルペジオにしたり。 - ベース音のタイミングを変える
今まで小節頭で弾いていたベース音をシンコペーションさせたり、サスペンドさせたり、一時的にベースを出さずにそこだけ音をわざと薄くしてみたり。 - ベースを細かく入れてリズミックにする
自分の手癖の一つなんですが、メロディやコードの間を縫うように細かくベース音を入れていったり。
メロディーに肉付けする
メロディーの肉付けについては、自分は以下のような手法を使っています。
- メロディーのタイミングを変える
シンコペーションさせたり、メロディーの頭の音を敢えて弾かなかったり、部分的にコードプレイに差し変えたり。 - 合間にアルペジオ・リズムプレイ等を入れていく
ギターはサスティンが短い楽器なので、メロディーがロングトーンで間が空く時など、アルペジオやリズム弾きで音を埋める処理を入れることも。
リハーモナイズ
リハーモナイズ(コードの付け直し)はソロギターに限らず、アレンジ全般において重要なテクニックです。
リハーモナイズについては、こちらの記事にまとめましたので、ご一読下さい。
ここでは、ゲーム音楽のソロギターアレンジのためのリハーモナイズということを考えましょう。
まず、ゲーム音楽は原曲イメージが大切なジャンルなので、原則、あまり極端なリハモはしません。挑戦的アレンジという趣旨ならその限りではないですが。
ソロギター演奏といことでいうと、リハーモナイズの目的は以下の2点に集約されます。
- 演奏性を上げる
- ギターで綺麗な響きが出るようにする
これって、前半でやった仮アレンジを作るための基本的テクニックと全く同じ目的ですが、アレンジを肉付けする段階で使いたいテクニックや音運びが出てきた時、それを実現するためにリハーモナイズは有効な手段になります。
――今回は自分のソロギターアレンジ手法を一気に解説しましたが、次回は「演奏」ということに目を移して、演奏テクニックを含めた自分のソロギター演奏スタイルの解説をします。
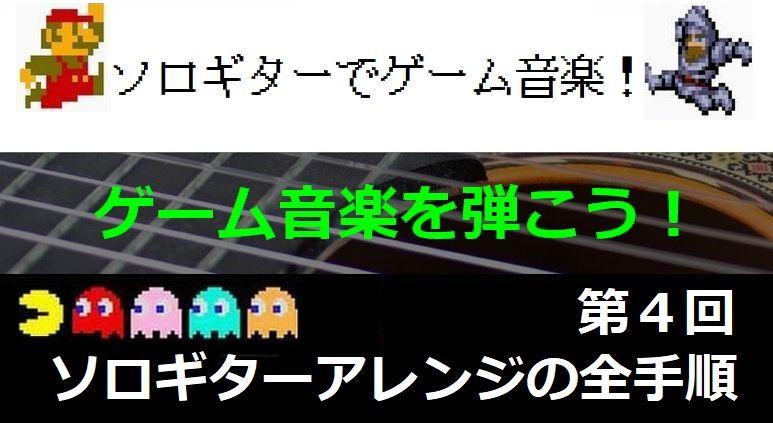
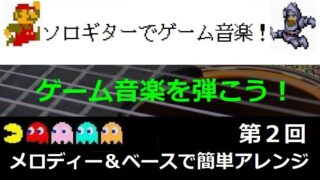

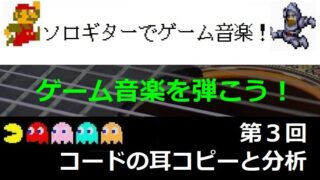
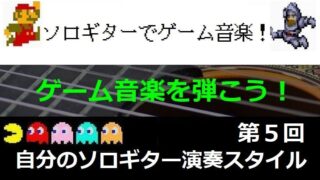
コメント