今日から新連載「ゲーム音楽を弾こう!」をスタートいたします。この企画は、ゲーム音楽を自分でアレンジして演奏してみよう!というものです。
初回は、初心者向けの選曲のしかたと、耳コピー(採譜)の基本についてお話します。
今回の企画を考えた理由
新連載「ゲーム音楽を弾こう!」をやろうと思ったのは、こんな理由です。
「自分もゲーム音楽演奏をやってみたいけど、難しそう」
「楽器をやり始めたばかりの自分でも弾けるようなのもやってほしい」
時折、視聴者様からメッセージやメールをいただいたりするんですが、そのなかで、このようなご意見が数件ですが寄せられておりまして、自分としてはずっと応えたいなあ、と思っていました。
今回の連載をやるに当たって、書きたいと思ったことはこんな事でした。
- 自分がどうやってソロギターアレンジを作っているか?
- どうしたらアレンジができるようになるか?
- どうしても出来ない部分をどう弾いたらいいか?
こんな感じで、ゲーム音楽やソロギターに限定しなくても、幅広い楽器プレイヤーに役立つ内容にしたいと思っています。
どんな人に向けて書くのか?
この企画はこんな人を対象に書いていきます。
- 何か楽器をやっている人
- ゲーム音楽演奏に興味があって、これから楽器をやってみたい人
- ゲーム音楽を耳コピーしてDTMなどでアレンジを楽しみたい人
こういった方を対象に、講座形式でやっていきたいです。
自分のやり方を軸に解説していくので、ソロギターアレンジの方法論が中心になりそうですが、他の楽器や打ち込みなどでも生かせるような内容を目指します!
講座の進め方
演奏までの流れとしてはこんな感じになります。
選曲→採譜→アレンジ→演奏
これから実際の流れにそってプロセスを1つずつ解説していこうと思います。
準備するもの
まず、ゲーム音楽の耳コピー・アレンジ演奏に必要なもの、あったほうがいいものを最初に書いておきましょう。
必要なもの
- 楽器
単音楽器でもいいのですが、自宅でソロ演奏を楽しむということを考えると和音が出せるものがベターです。 - 筆記用具
耳コピーのメモに使います。五線紙でもいいし、譜面を使わない人は普通のノートでも。PCやスマホでテキストエディタや譜面ソフトを使って記録してもいいです。 - 原曲音源
これがないと音を確認できません。
必要なものは以上ですが、何点かあったほうが良いものを追加します。
あったほうが楽なもの
- 譜面・MIDIファイル
これについては次の項目で書きます。 - DAW・波形編集ソフトなど
DAWや波形編集ソフトなどに音源をコピーしておけば、サーチや頭出しも楽々だし色々便利です。原曲音源の再生速度を変えられれば、速いフレーズの耳コピーも楽になります。 - 音楽理論とコードの知識
あるにこしたことはありませんが、そこまで知識がなくてもやってみよう!というのがこの企画の一つのテーマです。ゲーム音楽演奏から音楽を勉強してみるのもアリだと思います。ゲーム音楽はコンパクトにいろんな要素が凝縮されているので音楽学習の題材として大変優秀です。
譜面・MIDIファイルについて
メジャー曲であれば、楽譜やMIDIファイルの入手も可能と思うので、参考用・答え合わせ用として用意してもいいでしょう。
入手できれば耳コピーもかなり楽になります。
MIDIファイルの使い方ですが、まずはFinaleやMuseScoreなどの譜面編集ソフトに読み込んで譜面に展開します。
ただし、MIDIファイルの書き方によっては、符割りがグチャグチャになっていて解読困難だったり、譜面としてはまともに使えないものが多いので、ほんとに参考程度に。
ネット上にある譜面もMIDIも、個人が趣味でアップしているものが大半で、精度が高いものばかりではないので、音がちゃんと合ってるか?も、自分の耳で確認したほうが良いです。
ということで、譜面やMIDIがあったとしても、それを補助として使用しながら、一通りは耳コピーすることをお勧めします。
なにより自分の耳でコピーすると、曲の構造について色々と考えさせられるので、ただ譜面上で音を追うより格段に理解が深まります。
「自分でアレンジができるようになる」という目的を考えると、むしろ近道です。
初心者向けの選曲のしかた
耳コピーに入る前に、初心者向けの選曲のやりかたを解説します。選曲によってアレンジや演奏の難易度が全く変わってくるのでかなり重要です。
良くおぼえている曲
ゲーム音楽は刷り込み効果が強いので、好きな曲はほぼ空で歌えるんではないでしょうか。
メロディーを正確に記憶していると採譜もアレンジも早いです。
パート数が少ない曲
ゲーム音楽の中でも、レトロ系など和音数が少ないものは採譜が楽です。
ファミコン世代のものはメロディーが単旋律な場合が多いので、アレンジするときもメインメロディーをどれにするか、などで迷わなくてすみます。
なんですが、レトロ系の場合、アレンジでかなり肉付けしないと演奏として成立しない場合も多かったりで、全体の難易度は曲によります。
1ループが短い曲
1ループ1分以内くらいの短い曲のほうがとっつきやすいでしょう。
飽きっぽい人でも同じ期間に色んな曲に取り組めるので、モチベーションも保ちやすいです。
メロディーとリズムがわかりやすい曲
実際の難易度はやってみないとわからなかったりしますが、以下のような曲は最初は避けたほうが無難です。
- リズムが複雑で採譜に手間取るような曲
- メロの重要な部分が速いフレーズだったりする曲
- 転調が激しい曲
耳コピー・採譜の手順
次は、選曲した曲を耳コピー(採譜)してみます。
耳コピーのやりかたですが、頭から全パートをコピーしていこうとすると挫折しやすいので、メロディー→ベース→コードの順で個別にとっていきます。
全くの楽器・音楽初心者の場合はコードまでは難しいかもしれないので、コードが無理そうならコードの採譜と分析はとばして、メロディーとベースだけでアレンジに進むのもアリでしょう。
最低限の独奏アレンジはメロディーとベースだけでも作ることができます。
でも、コードを採譜してコード進行を分析・理解できないと絶対に壁にぶつかるので、やりながら少しずつでも勉強してコードをとれるようになったほうがいいです。
それでは耳コピー・採譜のプロセスごとに見ていきます。
メロディーを耳コピーする
以下の手順で、まずはメロディーから耳コピーします。
- 聴き込んでメロディーを覚える
この段階でリズムをとりながらやって、拍子を判断します。大抵は4拍子か3拍子のどちらかです。 - 手持ち楽器でメロディーを弾いてみる
このときはコードとかポジショニングとか気にしないでいいですが、音を探しながら、だいたいの調性=キーを把握しながら出来るとベストです。 - メモを作っておく
譜面が書ける人は譜面で良いですが、タブ譜でも良いし、弦やフレットの数をメモっておくだけでも。最初に小節線(4拍子なら4拍で1小節)を書き込んで、曲のどの部分かわかる形式にしておいてください。Aメロ、Bメロなどがはっきりしている場合はそれもメモ。
ベースラインを耳コピーする
メロディーと拍子がわかったら、ベースラインをとります。
曲中で一番低い音のパートを探して、音程をとっていってください。
レトロ系のゲーム音楽はルート弾きが多いのでわりと楽にとれると思います。
音程が判明したらベースラインをメモに書き込んでいきます。
ギターの場合は、6弦と5弦の2本でベースラインをとります。
実際の演奏アレンジでは4弦も使いますが、初心者の人は、ベースの音程を探す作業で6弦と5弦の12フレットくらいまでの音名(CとかDとか)をおぼえてしまうと良いです。
ベースラインがルート以外の音の場合もあるんですが、この段階では音だけとれればokです。
馴れればその音がルートかそうでないかすぐに分かるようになりますが、わからない場合、あとでコードをつけるときに判定すれば良いので。
ベースラインが複雑な場合
ベースラインがロングトーンやルート弾きや5度弾きなどではなく、動きがあってとりにくい場合どうしたらいいでしょう?
ベースラインを丸ごと耳コピーする
ベースラインを丸ごと耳コピーしてしまいます。
これは時間がかかりますが、一番確実ですね。
少しコードの知識があれば音の並びや他のパートの動きからコードが判定できます。
コードが判定出来ていると、後のプロセスが楽になるでしょう。
逆にコードの知識がない場合は丸コピーしても、どの音がルートやコードトーンなのか判定できないので、次の総当たり式のほうが良いかもしれません。
総当たりで試す
原曲の音源を再生して、ベースラインがわからない小節の頭から手持ちの楽器を鳴らして総当たりでマッチングする方法です。
何回もリプレイして色々な音を鳴らしてみて、一番しっくりくる音を探すという原始的方法です。
これ、原始的なんですが、耳とコード感鍛えられます。
見つけた音は、その小節のコードの、ルートか3度か5度の音の可能性が高いです。
たまに7度ベースやオンコードの場合もありますが、ここではマッチングできるベース音だけ見つけて、次のコード採譜・分析のときに考えてコードを確定します。
マッチングできる音が複数ある場合は複数書いておきましょう。全て次のプロセスの判断材料になります。
曲のキーを判定する
メロディーと大まかなベースラインを採譜できたら、何のキーでやってるか推測します。
この段階でキーがわかれば、コード採譜がかなり楽になります。
しかし、これが曲によっては難しいです。
基本的には、曲のなかで「終止感」のある所(大抵はメロディーの一番最後)のベース音がキーのルート音になっています。
ゲーム音楽はループするので終止しなかったりもしますが……
メジャーキーかマイナーキーかの判断は、その終止ポイントでそこで鳴っているベース音をルートにしたメジャーコード・マイナーコードを弾いてみます。
メジャーコードがマッチすればメジャーキー、マイナーコードがマッチすればマイナーキーです。
まあ、曲調からだいたいわかると思います。
スケール(音階)から判定する
スケールから判断する方法もあります。
その場合は、メロディーから使ってるスケールを判断します。
メジャースケール(明るい曲調)かマイナースケール(切ない曲調)になります。
そして、メジャースケールなら「ド」、マイナースケールなら「ラ」の音がキーのルート音です。
キーが分からない場合
調性が複雑だったりメジャー・マイナー以外のモードを使っている場合、キーがわからない場合もあるかもしれません。
キーがわからない場合は先にコードを採譜して、コード進行分析からキーを確定していくことになりますが、現段階ではあまり気にせずに「とにかく弾いてみよう!」でいいと思います。
弾いているうちにだんだんわかったりするものです。
――次回は「ゲーム音楽を弾こう!」というコンセプトにそって、今回メモった情報をもとに簡単アレンジで演奏してみましょう!
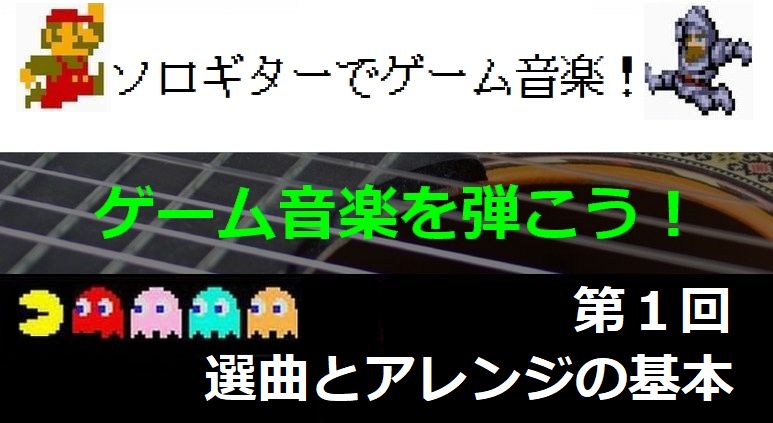
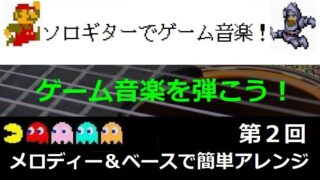
コメント