ゲーム音楽論では前回、ゲーム音楽の和音的な特徴をやりましたので、今回は音楽のもう一つの大きな要素である、音階(スケール)・旋法(モード)にも話を広げてみたいと思います。
ゲーム音楽は様々な表現が求められる
ゲーム音楽の独自事情として、ゲームの世界観やシチュエーションに合わせた古今東西様々な表現が求められるということがあります。思いつくままに挙げてみましょう。
- ファンタジーRPGの中世的世界観
- SF的未来的世界観
- エキゾチックな異国情緒
- 和風な世界観
- ホラーで恐ろしげな雰囲気
- 田舎ののどかな情景
- 都会の洒落た雰囲気
- 勇ましいバトル曲
- 極限状態の表現
- 宗教的色彩
いくらでも出てきそうですが、ゲーム音楽では様々なジャンルのフレーズやアレンジを駆使してこういうものを表現をしなければなりません。
色々なスケール(音階)を知っていると、表現の幅を広げたい時に使用する音階を吟味する事で、比較的手軽に楽曲全体を特定のカラーに寄せる事も可能になるのですが、今回はそのあたりを掘り下げてみようと思います。
基礎的な調性音楽の音階等
音階の話をするに当たって、予備知識として一般的な西洋音楽で使われる音階の基礎を知っておいたほうが良いと思います。
西洋音楽で使われる音階の基礎的概念である、メジャースケール・マイナースケール・ダイアトニックスケール・モード(旋法)・コードスケールなどについて、フラメンコギターブログの「音楽理論ライブラリー」にまとめてありますので、参考にしてください。
ゲーム音楽に限らず西洋的な響きを持つ音楽は、原則として①メジャースケール、②3種のマイナースケール、③7種のモードスケール、④その他の各種コードスケール、といった基礎的な西洋音階で作られているのですが、そういうノーマルな部分の成り立ちは上にリンクした記事を読んでいただくとして、今回はゲーム音楽特有のニーズに関わるイレギュラーな音階の使い方に的を絞って解説していきます。
モードを活用したゲーム音楽
西洋音楽のほとんどは長調か短調の範囲内(転調含む)で作られていますが、例外も存在します。その代表的な例がモードスケール(協会旋法)のイレギュラー活用です。
モードスケールの応用的な使い方をこちらの記事で解説していますが、モードスケールはダイアトニックスケールに転用される他に、各モードの独自の響きに着目したイレギュラーな活用をされることがあり、そうした手法はゲーム音楽でも多く見られます。以下に実例を挙げてみましょう。
①Ⅰコードにリディアンを当てる(グラディウス「空中戦」など)
②Ⅰmコードにドリアンを当てる(LIVE A LIVEメインテーマなど)
③ⅠmやⅠ7コードにフィリジアンを当てる(スパニッシュぽくなる)
④同一コード上でスケールを切り替えて「モードチェンジ」を強調する(ロマサガ3「四魔貴族2」エオリアンとフィリジアンのモードチェンジを使用)
こういうものを転調と捉えるのか、モードスケールのイレギュラー活用と捉えるのかは微妙な場合も多いのですが、メロディーの動きや前後のコード進行などから判断します。
民族音楽系音階
ここまでは西洋音楽を前提にお話してきましたが、世界には西洋音楽理論の守備範囲外にある音楽も数多く存在します。
そういうものの代表が、民族音楽系の音階です。
それらは大抵、独自の楽器やフレージングとセットになっているものなのですが、特定の地域・時代などの雰囲気を表現するにはゼロから創造するより、そういう伝統的なものを取り込むほうが早いので、ゲーム音楽でも民族音階が活用される頻度はかなり高いのではないでしょうか。
なお、民族音階をはじめとする特殊音階について、こちらの記事で詳しく解説していますので予備知識として読んでいただけるとより理解が深まると思います。
ここでは、ゲーム音楽での民族音階使用例を挙げていきます。
インド・アラブ・スパニッシュ系統
インド・アラブ・スパニッシュ系統の音階は♭2nd音を含むのが特徴で(♭2を含まないものもありますが)、フレージングは♭2からルートへの半音下降解決が基本です。
インド・アラブ系の音楽を採り入れたゲーム音楽は、古くは『ピラミッドの謎 エルギーザの野望』や、ドラクエ3のピラミッドのテーマなどがありますよね。
スパニッシュ系は「ミの旋法」と言われるようにフィリジアンモードと近いのですが、ロマサガバトル曲のようにメタル系アレンジと組み合わされたりもします。
和音階系
伝統的な日本の雰囲気を出すために和音階(陰旋、陽旋、ヨナヌキ、琉球音階とか)を使ったゲーム音楽も数多いですよね。和音階を使用している初期のゲーム音楽には以下のようなものがあります。
- 影の伝説
- 奇々怪々
- 源平討魔伝
- 月風魔伝
- がんばれゴエモンシリーズ

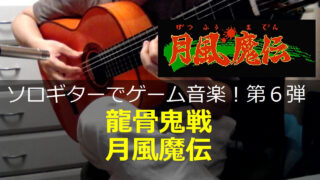
ちなみに、東方Projectシリーズの音楽は、和音階+激しいピアノバッキング+テクノロック系ビートという組み合わせが多いのですが、これもまた「日本のゲーム音楽」と言う以外に表現し難い組み合わせですよね。
ブルーノート系
ブルーノートはアメリカに奴隷として連れて来られた黒人の音楽(黒人霊歌)を起源とするメジャーでもマイナーでもない音階です。
ブルーノート系の音階の起源を辿ると、もともとはアフリカ起源の民族音階と言えるものですが、ブルース、ジャズ、R&B、ソウル、ファンク、さらには白人文化であるカントリーやロックンロールなど、アメリカ起源の音楽全般に使われていて、アメリカが文化や経済でリーダーシップをとるようになると同時に全世界に波及しました。
ブルーノート系の音階としては、ブルーノートペンタトニックスケールが有名ですが、ブルースで使う音を全て含むブルースメジャースケールというものもあります。
ゲーム音楽ではクラシック系の勢力が強いので、相対的にブルーノート系音階の使用は少ない印象なのですが、自分が採譜した中だと初期ナムコの大野木宣幸さんや、セガの川口博史さんがブルーノート使用が多いように思いました。
今まで演奏した中では、ニューラリーXのメインBGMやファンタジーゾーンの1面・4面などでブルーノートが出てきます。
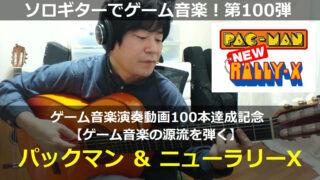

その他の民族系音階
今挙げた他にも、民族音楽系の独自音階は世界中に星の数ほど存在しています。
音階の音数も西洋的な7音階とは限らず、例えば、フォルクローレの音階とか、和音階とか、中国伝統楽曲の音階などに代表されるように、民族系音階は総じてペンタトニック(5音階)が多いですよね。
そういう特殊音階をここで全て解説は出来ませんが、特殊音階を使用している曲を演奏した時に動画解説ページで個別解説していこうかと。
ゲーム音楽は、MIDIの打ち込みのみで完結することも出来るので、そこまでの専門知識が無かったとしても、民族音楽など特殊なフォーマットの音楽を感覚的・実験的に取り入れやすいという強みはあると思います。
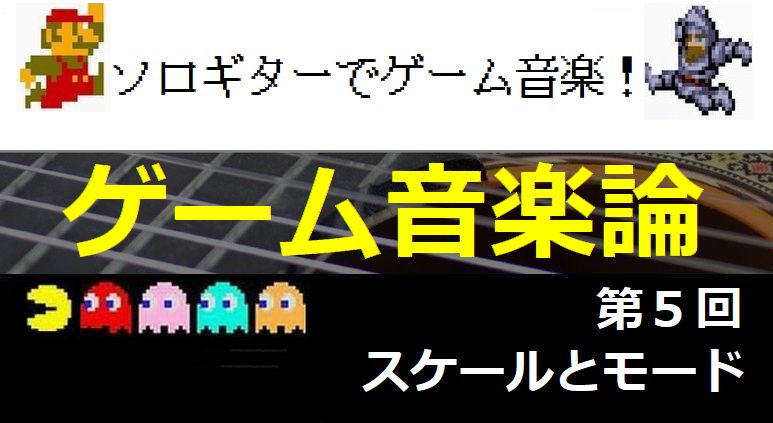

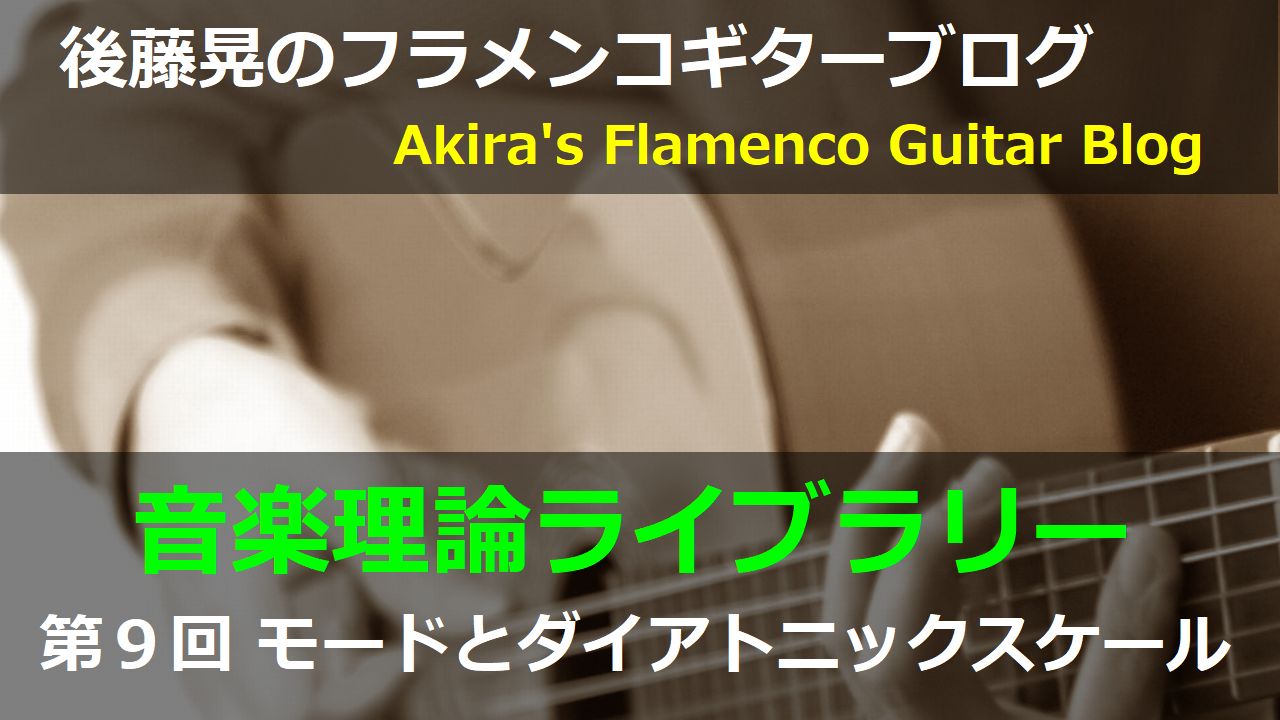

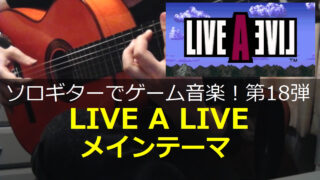

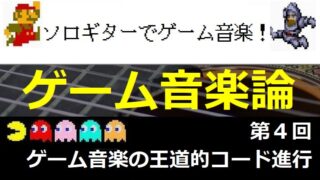

コメント